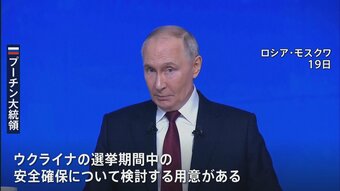■FRBの「歴史的失敗」の可能性も
アメリカの6月の消費者物価指数は前年同月比で9.1%伸びており、予想を上回り、加速している。これをどう見たらいいのか。
熊野英生氏(第一生命経済研究所 首席エコノミスト):オイルショック以来のものすごいインフレです。アメリカは3月以降急激に利上げしているのですが、いまのところ全く効いてないという数字が9.1なのだと思います。

アメリカではありとあらゆるモノが値上がりしているがどう見る?
第一生命経済研究所 熊野英生首席エコノミスト:
日本ではガソリン、電気、食品が値上がりしていますが、アメリカは航空運賃や新車、住居にも及んでいます。新車は半導体が手に入らないので納品が半年、1年と遅れる。したがって中古車も売れるという、供給不足で価格が上がっています。住居も木材や金属が高いから高騰している。新車と住居は世界経済の構造が、需要が強いからインフレというよりは供給不足、例えば対ロシア制裁の影響や対中国の経済安保などで物流が滞っていると。だから、そう簡単に物価下落に転じない。供給側のインフレが後ろにあるのだということを物語っているのではないか。

一方、FRBは今年3月から3回利上げしてきた。今回の消費者物価指数9.1%ショックを受け、さらに1%利上げするのではないかとの観測が出て、株価も急落する局面があった。FRBの対応は難しくなっている。
第一生命経済研究所 熊野英生首席エコノミスト:
インフレに対していままで薬を飲んできたが、効かないからもっと強い薬を飲むのではないかということで出たのが1%。連邦準備銀行の総裁などは0.75%と火消しに回ったのですが、22年の12月まで毎月0.75%ずつ上がるのではないかという恐怖感も市場にはあると思います。

ここまで急激に利上げすれば、景気が後退するのではないかとの懸念が出る。そこで出てきているのが「スタグフレーション」という言葉だ。FRBのパウエル議長は物価が下がって、景気は落ちないという「居心地の良い景気後退」を目指しているが、中々、そうはいかないと見ている人が増えてきている。
第一生命経済研究所 熊野英生首席エコノミスト:
FRBは今回、歴史的に失敗する可能性があります。これは引き締めが遅れたというのもありますが、オイルショックの時も同じでしたが、供給側の要因でインフレが高止まりしているので、利上げしてもなかなか効かない。利上げするとインフレ率は高止まりして景気が悪くなる。これがいまアメリカを中心に真実味を増しているスタグフレーションの図式です。