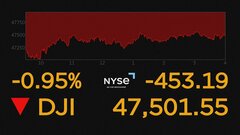ここでは、シャーデン・フロイデ(他者の不幸に対する快感)が、単なる敵意や嫉妬によって生まれるだけでなく、強い愛情や絆といったポジティブな感情の裏側からも生起することを明らかにする点にある。
とりわけオタク文化における「推し」との関係性は、対象への深い感情的関与を前提として構築されるため、シャーデン・フロイデが発現しやすい独自の心理的土壌を有している。
オタクが抱えるシャーデン・フロイデを大きく二つの類型として整理する。
第一に、限定的資源(席、グッズ、接触機会)をめぐる競争環境が生む“他者オタクへの敵意型”シャーデン・フロイデ。
第二に、推しへの強い愛着や理想化が裏切られたと感じたときに発生する“反転アンチ的・愛憎転化型”シャーデン・フロイデである。
とくに後者は、愛情の喪失や理想との不一致が攻撃性へと転化する心理過程を含み、推しに対する憎悪がどのように生まれ、いかに自己防衛として機能するのかを理論的・事例的に考察する。
なお、ここでの議論は筆者自身のこれまでのエスノグラフィ的観察や自身の経験を基盤としており、オタク文化を俯瞰することを試みた一つの私論である。
普遍的に書いたつもりではいるが、ここで述べた現象や要因がすべてのファンやすべての推し関係に当てはまるわけではないことに留意したい。
また、特定の推し活のあり方を価値づけたり否定するものではないことも重ねて留意したい。
他人の不幸で今日も飯が美味い
シャーデン・フロイデという言葉を聞いたことがあるだろうか。
freude(喜び)とschaden(損害・毒)という言葉から成るドイツ語である。
日本語では「人の不幸は蜜の味」や「メシウマ(他人の不幸で今日も飯が美味い)」などがこれにあたるだろう。
自慢話をしているいけ好かないやつが失敗しているのを見るとうれしいと感じる者も少なくないだろう。
ドイツの哲学者イマニュエル・カントによれば我々は「他人の幸福が自身の幸福を少しも損なうことないのに、他人の幸福を見る事に苦痛を伴うこと」があり、それを嫉妬と定義している。
基本我々は利己主義であり、他人より自分が劣っていることが苦痛で仕方がないのである。
それゆえにシャーデン・フロイデのような誰かが失敗した時に思わず湧き上がる喜びの感情が生まれてしまう。
“愛憎転化”
一見すると、この感情は単なる悪意や妬みの表れのように見える。
だが、近年の心理学や脳科学の知見によれば、シャーデン・フロイデは「敵意」だけでなく、「愛情」や「絆」といった、むしろポジティブな感情の裏側からも生まれることがあるとされている。
脳科学者で『シャーデンフロイデ』の著者でもある中野信子は、「妬み」という感情の背景には「オキシトシン」が関与している可能性があると指摘する。
オキシトシンとは、脳下垂体後葉から分泌されるホルモンの一種で、「幸せホルモン」としても知られている。
このホルモンは安心感や信頼感を高め、人間関係を円滑にする働きを持つとされ、その主な役割は、人と人とのつながりを強化し、愛着を形成することにある。
他者との間に特別な情緒的絆が生まれるとき、脳内ではオキシトシンがその回路の形成に関わっている。
しかし近年の研究では、このホルモンが必ずしも「優しさ」や「幸福」だけをもたらすわけではないことも明らかになっている。
オキシトシンは、絆が脅かされたときに「自分の集団や関係を守ろう」とする防衛的な行動を強める作用も持つ。
言い換えれば、人と人とのつながりが切れそうになるとき、オキシトシンはそれを阻止しようとする反応を促すのである。
「離れないでほしい」「関係を終わらせようとするのを許せない」といった衝動は、その作用の表れといえる。
また、Cikara&Fiske(2013)によれば、人は「自分が感情的に関与している対象」ほど、その対象が失敗したときにシャーデン・フロイデを感じやすいことが確認されている。
これは単なる「敵意」ではなく、むしろ関係性の深さそのものが引き金になっているという点で、愛情や絆と密接に結びついているといえる。
それゆえに、対象への強い愛着は、ときに嫉妬や攻撃性を伴う。
他者への愛情が深くなるほど、関係が理想どおりにいかなくなったときの不安や怒りも強まる。
心理学的には、こうした状態は「愛憎転化」や「アンビバレンス(両価性)」として知られている。
好きな人が自分の理想から外れたとき、「失望」や「怒り」が生まれ、その相手が不幸になると、無意識のうちに“自分の感情を正当化する”ための安堵を感じてしまう。
つまり、「自分が裏切られた」と感じる痛みを軽くするために、「ほら、うまくいかないでしょ」と思うことで心理的なバランスを取っているのである。
これは一種の自己防衛反応であり、愛情が強いほど、その反応も強くなる傾向がある。この心理の背後には、次のようなフローがある。
オキシトシンの分泌 → 愛情・絆の深化 → 理想と現実の不一致(愛が必ずしも成就しない) → 愛憎転化(愛情が裏切りや失望によって敵意へと転じる) → ネガティブ感情の増幅 → シャーデン・フロイデ(他者の不幸に対する安堵・快感)の発露
つまり、オキシトシンによって形成された深い愛着が、関係の破綻や理想とのズレによって“防衛的な攻撃性”へと転じる。
その結果、相手の不幸を見て「ほら、言ったでしょ」と感じる。
それは他者を罰したいというよりも、自分の理想を裏切られた痛みを和らげるための心理的自己防衛として機能する。
そして、愛情が強いほど、こうした愛情起因型のシャーデン・フロイデも強くなる傾向があると考えられている。
他のオタクに対するシャーデン・フロイデ
ここから、例えばオタクにおいては、オタ活を進めていく中で2つのシャーデン・フロイデが生まれると筆者は考える。
まず1つ目は、他のオタクに対する敵意によって生じるシャーデン・フロイデである。
他人の経験やコレクションに嫉妬し、敵意を抱いている相手が失敗したとき――たとえば、ライブの席が自分より悪かったり、レアなグッズを手に入れ損ねたりしたときに、「ざまぁ」と感じて心理的優位性を得るケースだ。
この現象の背景には、オタク市場の構造的な特性がある。
ライブには定員があり、グッズや握手券などの有形物も需要が供給を上回ることが多い。
日用品のようにすべての消費者の手に渡るほど十分に供給されることはなく、ファンはその限られたパイを奪い合うことを余儀なくされている。
そのため、独占欲求や他者排他、同担拒否、マウンティングが生まれやすく、他人を敵視せざるを得ない市場環境そのものが、シャーデン・フロイデを生み出す要因となっているのである。
推しに対するシャーデン・フロイデ
一方で、筆者はオタクの消費性から、オタクとは自身の感情に「正」にも「負」にも大きな影響を与えるほどの依存性を見出した興味対象に対して、時間やお金を過度に投じ、精神的充足を追求する人、と定義している。
つまり、推しという存在を内在化し、当事者意識をもって消費している存在だといえる。
たとえばアイドルオタクであれば、アイドル自身と自分の理想像(=理想の消費対象)を重ね合わせたり、推しのインタビューからその将来像や理想像を“自分なりに構築”するなど、推しの人生そのものを自分の内側に取り込むような感情的関与を示す。
その結果、「推しを成功させるためには応援が必要だ」「自分が買い支えなければならない」といった責任感や使命感が芽生える。
こうした当事者的な心理は、アイドルの成功を「自分ごと」として捉える意識に支えられている。
一般的な消費者には見られないこの消費性は、コンテンツに対する能動的な関与度の高さによるものである。
コンテンツそのものが生きる上での中心的な意味を持ち、「ワタクシゴト」――つまり、嗜好対象との関係が自己の主要な関心事となり、他人事ではなく能動的に関与する態度へと変化していく。
筆者は、この「ワタクシゴト」こそが、オタクのコンテンツ依存性を生み出し、さらにシャーデン・フロイデをも引き起こす心理的要素であると考える。
現実の生活において、自己実現や人間関係の充足が得にくい時代に生きる私たちは、しばしば社会的な枠組みのなかで立ち止まり、行き場のない停滞感や喪失感を抱えている。
そうした現実の不全を補うように、コンテンツが“もう一つの居場所”として機能し、生きる意味の一部を担うようになっているのだ。
そして同時に、コンテンツは希望としての力も持っている。推しの存在や作品の世界は、日常の閉塞を一瞬だけ忘れさせるだけでなく、「自分ももう少し頑張ってみよう」と思わせる小さな再起のきっかけとなる。
それは現実からの逃避であると同時に、現実と再び向き合うための支えでもある。
また、目的を見失い、ただ時間の流れに身を任せていた人にとって、「推すこと」そのものが新たな生の目的となることもある。
推しを応援する日々の行為が、生きていることの実感をもたらし、気づけば“推しの存在を軸にした生”へと再構築されていくのだ。
推し(コンテンツ)の存在が生きる意味の一部となっているほど、推しを内在化しやすくなる。そして、推しの存在そのものに強い当事者意識を持っているために、理想通りの「消費」ができないと、内的な葛藤が生じるのである。ここでいう「理想通りの消費」とは、
(1) 欲しいと思ったものを逃さずに手に入れられるか、
(2) 消費対象である“推し”が、自分の理想像どおりであるか、
――この2点を指す。そのどちらかが崩れたとき、オタクは「自分の理想が裏切られた」と感じ、愛憎入り混じる複雑な感情を抱くようになる。