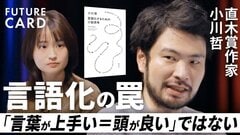誰しもが、他の誰かの欲望を掻き立てる
これは、一見すごく抽象的な議論に見えるが、他人の投稿を見て「いいな」と思い、マネして購入して、それを投稿したモノを他の誰かが見てマネして購入していく、といった連鎖は、SNSにおける他人の消費を参照して自分も買うというサイクルそのものでもある。
SNS以前から顕示的消費のように他人に見せつけるための消費は行われていたが、文字通り実際に「会う」という対面でのコミュニケーションが「羨ましい」「羨ましがらせたい」という感情を生むために必要だった。
もちろん手紙で〇〇を買ったと記す、人づてに自慢話を聞くといった手段もあるのは確かだが、羨ましいと思ってもらう手段と範囲と対象に限りがあった。
一方でSNSは投稿者の意図の有無は関係なく、流れてくる情報のすべてが「羨ましいと思ってしまう」情報になり得るため、だからこそ、常に自分は誰かにとっての承認欲求を満たす手段となっていくのである。
いつでも他人との境遇の差を意識させられ、いつでも見せびらかされていて、それでも他人を参照し間違いない選択をしたいから、受動的に「それが自分にとっても幸福になる」と益々他人の価値観を受け入れていくこととなる。
現実社会(オフライン)においては、自身の消費結果が他人の新しい幸福=羨ましさを誘発しない場合の方が本来ならば多いはずである。
今筆者は森永のミルクココアを飲みながら執筆しているが、私の周囲の誰も私が何を飲んでいるかなど気にもとめていないし、私が飲んでいることが新たな需要を生み出す気配もない。
しかし、SNSに一度投稿されてしまえば誰かしらにとっての「いいな」になり得る。
そして、他人が買ってよかったと思うモノを自分が持っているという事実が幸福に繋がるような、他人の承認や他人の反応そのものが購買動機や満足に繋がっていく人々にとっては、この三角形は飽くことなく生み出されていく。
そのような他人の欲望に溢れているSNSにおいては、他人が他人の欲望を模範して幸福を得ていることも可視化されていく。例えばコンビニで買った最新スイーツが美味しかった、といった旨の投稿を誰かがしたとしよう。
その投稿が拡散され何万もの「いいね」がついているのをみたら、あなたは多くの人がその商品を「いいな」と思っているという事を認識するはずである。
この投稿者が満たした欲求=実現した幸福に何万もの人々が羨望のまなざしで見つめ、自分も消費(マネ)したいと思っている他人がたくさんいることを知るわけだ。
ある意味関心の持たれる投稿は他人にとっての新しい欲望そのものであり、あなたは他人の中に新たな欲望がうまれた瞬間(きっかけ)を知ることとなる。
また、その投稿を模倣した者は、自分自身も、消費を行う事で欲望を充足した=幸福を達成したことを投稿するため、それが次々と積み重なる結果、その投稿に対する信憑性が確たるものになるわけである。
これが所謂「バズっているから欲しくなる、バズっているから間違いない」と感じて消費欲求が駆り立てられる構造であると筆者は考える。
また、他人が新しい欲望を見出したことを模倣するように、その投稿に「いいね」し、その欲望を満たすためにそのスイーツを消費し、幸福感に繋げる。
そんなサイクルも溢れているからこそ、SNSによって(1)他人が満たした欲望を私も満たしたい、というサイクルと、(2)他人が他人の欲望を模倣しているから自分も模倣して幸福になりたい、という2種類の形で他人を顧みた消費が生まれていると筆者は考えるのだ。
このSNSで生まれる「情報」「消費」そして「幸福」というサイクルによって私たちは消費を媒介に繫がりを見出した。
皆が同じようなモノを購入し、皆が同じような投稿をし、それがトレンドであると認識したり、トレンドのモノを消費していると実感することになる。
一方で、自身の満たした幸福を他人に見せびらかすことで承認欲求を満たす者もいる。「いいね」というツールがあることでわかるように、そもそもSNSは他人の羨望を引き出すことを目的としている側面もある。
他人に自身の生活を切りとったものを見せつけて自慢することは決して悪い事ではないが、「羨望」は不幸を生み出すトリガーでもある。
簡単にマネできるようなことならそこまでの嫉妬心は生まないが、羨ましいという感情を持った当人が、その羨ましいと思った源泉=情報(他人が達成した欲求)を達成するのが困難であればあるほど嫉妬心を生む。
逆に羨ましいと思われるものほど達成する事が困難であるため、これだけ多くの羨ましいが溢れているSNSは自分自身がそれを達成するのが困難であるという現実を日々再認識させられてしまうツールでもある。
このことから筆者は、SNSは「人と比べる社会」を生み出したと考えるのだ。
※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員 廣瀬 涼
※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。