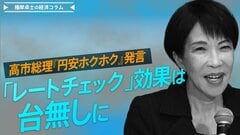Z世代を意識した政策・施策設計への足掛かり~身近な「思いやり」をどう物語として伝えるか
1|ビジネスで求められる実践的アプローチ
ここまでの分析から見えてきたのは、Z世代がサステナビリティに対して行動しにくい理由が、単なる「無関心」ではなく、日本特有の文化的・社会的構造に根ざしたものであるという点である。
それでは、このZ世代に対してどのような政策・施策的なアプローチをとるべきだろうか。これまでの分析を踏まえると、次の4つの視点が重要であると考えられる。
1. 身近な利他を訴求する
「環境を守ろう」といった大きな目標ではなく、日常に近い「小さな利他」を通じて共感を呼ぶことがカギとなる。近い将来や身の回りの人々に関わるテーマの方が、Z世代にとって「自分ごと」として捉えやすい。
2. 規範を見える化する
「みんながやっているから自分もやる」、そうした空気感の形成が行動を後押しする。SNSやメディアを通じて、同世代の参加者の声を可視化して、「やるのが普通」という規範をつくっていくことが有効と思われる。
3. イメージを刷新する
サステナビリティを「真面目で堅い話」から、デザイン・ファッション・テクノロジーと結びつけた「ポジティブな選択肢」へと転換することも求められる。
「意識高い系」と揶揄されるのを避けるには、楽しさやセンスの良さを感じられるスタイルとして提示する工夫が必要となる。
4. 身近な善意を大きな意義につなげる
「この行動が、社会や未来にちゃんとつながっている」というストーリーがあることで、モチベーションが高まる。
Z世代にとっては「自分のため」が結果的にサステナビリティに繋がる、という形が受け入れやすい。
少なくともこの4つの観点を意識することで、サステナビリティを「押しつける」のではなく、Z世代の感性と調和した形で「受け入れやすく」、持続的に「育っていく」アプローチに近づいていくと思われる。