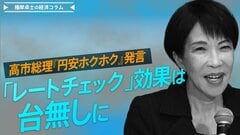Z世代の「意識高い系=サステナビリティと距離を置く姿勢」という解釈は本質を見誤る
今回取り上げたデータは、サステナビリティに対する性別や世代ごとのイメージや動機づけが異なることを示しており、政策・施策という観点では、性差・世代差を踏まえたアプローチが求められる点は改めて指摘したい。
その中で、Z世代による「意識高い系」という評価については、やや慎重に捉える必要がある。
データ上はむしろ、彼らがサステナビリティやSDGsについて学び、理解している世代であるにもかかわらず行動が伴わないのは、利他性に対する文化的距離感や、世間・SNSによる規範圧力、そして欧米型「共通善」と日本的「世間」とのズレを認識しておく必要がある。
Z世代は、そのジレンマを背景に「意識高い系」と表現しているにすぎず、その言葉を「サステナビリティの価値観と距離を置く姿勢」と短絡的に解釈してしまうと、本質を見誤るリスクがあるとも言える。
だからこそ、Z世代を動かすには、「日本の文化や感性に合った形でサステナビリティを伝える工夫」が欠かせない。
本稿では、そのための4つのアプローチを例示したが、シンプルに言えば、未来や地球といったスケールの大きな話を、そのまま語るのではなく、日常生活や身近な人間関係に結びつけた「物語」として翻訳することが重要だということだろう。
そうした翻訳があるからこそ、学校教育などを通じて「サステナビリティを知ってはいる」Z世代の意識が、少しずつ「行動する」という実践へとつながっていくのではないだろうか。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 准主任研究員 小口 裕)
※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。