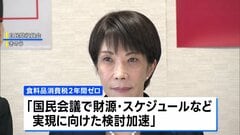価格高騰の責任は、日銀にもある
こうした円安の背景には、日本の政策金利が欧米中央銀行よりも低いことが挙げられる。円安に歯止めをかけられるのは日銀の政策運営に依存する部分も大きいのだが、中小企業経営や財政事情を考えると、日銀の利上げのペースは緩慢になり、将来に到達する政策金利水準(ターミナル・レート)も低くなってしまうのだろう。
かつて、物価は日銀がコントロールできるものだというリフレ的な発想で、黒田緩和が始まった。その結果として過剰な円安・輸入インフレが進んだが、今に至ってその弊害について「日銀がもっと物価引き下げに向かってコントロールすべきだ」という議論にはなってはいない。
筆者は、インフレの責任はすべて日銀にあるという考え方はしていないが、現状よりも影響力を行使して、食料品などの輸入と関連性の高い品目の物価上昇率を抑えてもよいと考える。
かつてインフレを起こせ、と威勢よく述べていた人々は食料品インフレの責任をうやむやにしている。日銀も、最近になって植田和男総裁が、食料品価格高騰の悪影響に遅ればせながら言及し始めた。物価対策は、財政出動ではなく、金融政策をもっと機動的に使うことで実施してほしい。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生)