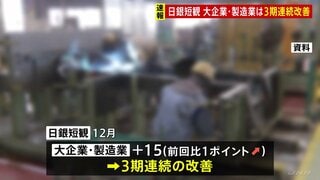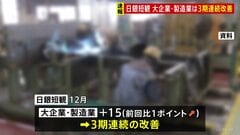制度のインフレ調整
最初に「制度のインフレ調整」の観点。与党案の「123万円」という数字は基礎的支出項目の物価上昇率を参照したようだ。先の控除額改定時(1995年)からの物価は、食料品や光熱費など“生活必需品”の性格を有する品目がより高い上昇率となっており、それに沿った改定になる点でCPI総合指数による改定よりも趣旨に沿ったものであると考える。国民民主党の提案した最低賃金をもとにした「178万円」とは大幅な乖離が生じることにはなるが、「制度のインフレ調整」としては一定の理があるものだろう。
しかし、課題だと考えるのは住民税の基礎控除額引き上げの見送りである。地方財政への配慮が主な理由とみられるが、そもそもの所得控除の理念のベースである“最低生計費を非課税とする”考え方からすれば、住民税をその対象外とする理は立たない。制度のインフレ調整の観点で中途半端な内容になっている。 住民税の控除額は多くの制度で低所得者(住民税非課税世帯)を区分するための線引きにもなる。社会保障などにおいても住民税非課税世帯により多くの給付を行うように傾斜をかけている制度は多い。基礎控除は国民健康保険の保険料算定の際の計算根拠にも用いられている。住民税の控除見直しは単に地方税の減税だけにつながるだけではなく、影響の及ぶ制度が多岐にわたる。所得税に比べて考えなければならなくなることも多い点は事実である。
しかし、だからといって住民税の基礎控除を見直さなくてよいという話にはならないだろう。むしろ様々な制度において低所得者の線引きに用いられてるラインだからこそ、物価や賃金の上昇の中で見直すことが必要なものであり、地方財政への配慮を理由に見送るべきものではない。見直しを行わないことで、「本来は低所得者とみなすべき人を低所得者としてみなすことができてない」という現状を放置することにもなる。与党案の場合、国民民主党案の178万円への引き上げに比べれば、地方税減少の影響は遥かに小さくなるほか、難しいのであれば国からの財政補填も考えうるだろう。