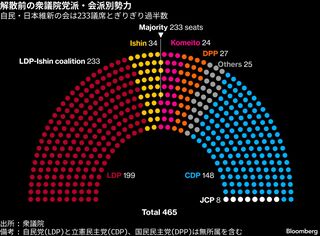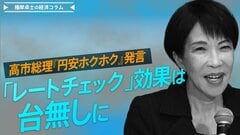会社視点の働き方改革から生き方改革へ
このように、現状では企業が副業・兼業の導入には課題が残されている。しかし、副業・兼業の導入は、従業員が働きやすい環境を実現することで、離職率の改善などが期待できる。ソフトウェア開発を行うサイボウズでは長時間労働などによる従業員の離職や知名度の不足による採用難に陥っていた。しかし、副業・兼業の自由化を含む働き方改革を行ったことで、離職率を28%から4%まで大幅に改善した。同社の働き方改革は「都合に合わせて働く場所と時間帯を選べるウルトラワーク」、「最大6年の育児休暇」、「副業(複業)の自由化(誰でも会社に断りなく副業可)」といった非常に大胆な内容となっている。
同社では「100人いれば、100通りの人事制度があってよい」との方針のもと、従業員一人一人の個性が異なることを前提として、一人一人が望む働き方や報酬を実現させることを目指した。
この結果として、従業員は収入を増やすだけでなく人脈を広げスキルを高めモチベーションを維持・向上できるといったメリットが得られたとしている。現在では様々な人が働くようになっているため、画一的な制度ではなく一人一人の状況に合った施策を行うことが、従業員の満足度やエンゲージメントの向上につながる。
現在では、働く人のライフスタイルや働き方が多様化する中で、企業の人材戦略もそれに適応していくことが求められている。日本の従来型の労働制度や慣習のもとでは、労働者は受動的な長時間労働を強いられることも多い一方で、それ以外の選択肢も少ない状況が続いてきたと考えられる。しかし、現在では、副業・兼業をはじめ様々な働き方を選択できる環境に変化しつつあるかもしれない。
こうした中、食品メーカーのカゴメは「世間で言ういわゆる働き方改革は『会社視点』である」と指摘している。働き方改革を考える際に意識されているのは、会社がいかに「生産性を上げられるか」だが、個人は自身のquality of life(QOL)の向上を考えるため、ギャップが生まれる。全ての人が家族との時間や自己研鑽など自身のやりたいことを犠牲にせず充実した生活をおくることができることを目指す「生き方改革」が望ましいとしている。
働き方改革を推進していく上で、企業や政府による環境整備だけではなく労働者自身が能動的に自分自身の働き方や暮らし方を考え、選択していくことが個人のQOLの向上につながると考えられる。
また、働き手の確保が難しくなるとともにその考え方や性質が変化している現在において、企業は人材戦略を柔軟に再構築していくことが求められる。
多くの人が副業・兼業により自身が望む働き方と生き方を実現、活躍していく事がイノベーションの創造や高い生産性を実現し社会を変えていく事につながるかもしれない。副業・兼業に関する動向に引き続き注目したい。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 金融研究部 准主任研究員・ESG推進室兼任 原田 哲志)