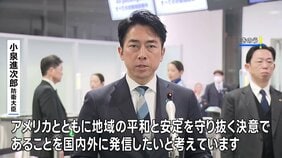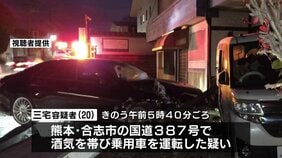養鰻業者も「ひとまず安心」

今回の採決を、固唾を飲んで見守っていたのは、ウナギ店だけではありません。
福岡県福智町に、2023年に開業した養鰻場です。

15台の養魚池を完備し、年間10万尾を福岡県産のウナギとして出荷しています。

福岡県で最大規模の養鰻業者で、ウナギは、体長15センチほどに成長した「クロコ」と呼ばれる稚魚をフィリピンから輸入し、1年から1年半かけて育てます。

小売店に卸し、ふるさと納税の返礼品にも選ばれ、12月から一般向けの販売を始める予定でした。

宝美養鰻場 大塚弘典 統括本部長
「(国際取引規制は)大きく注目すべき点でありまして、やはり検疫の検査であったり、輸出にかかる時間、コストが上がってくるっていうことは、マイナスになるかと捉えていました。(規制で)DNA検査が本当にされてっていうところであれば、(稚魚の価格も)2割ぐらいは上がるのかなという風に思っています。そこがおのずと販売に2割以上乗ってくるということになり得る。(否決で)ひとまず、ちょっと安心したなっていうところではあります」
インフラ代・エサ代の高騰が経営を圧迫

国際取引規制の否決で安堵はしているものの、現状の養鰻業を取り巻く環境は楽観視できるものではないと言います。
それが、インフラ代の高騰です。
宝美養鰻場 大塚弘典 統括本部長
「ガス代、電気代、すべてね、重油もそうですし、インフラの関係が全て高騰している状況がありましたので、かなり厳しい状況ではあります」

難しいのは水温調整、井戸水を温め、25度から27度に保つ必要があるため、ガス代などの高騰は経営に直結すると言います。
また、国産の餌代も合わせて高騰しているため、規制の否決を心から願っていました。

宝美養鰻場 大塚弘典 統括本部長
「また力を入れて、育てる方に専念しようと思います」