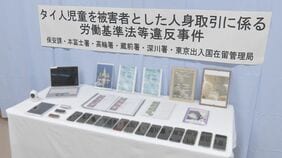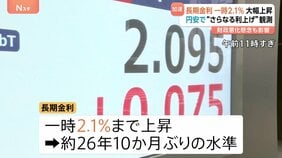両親に精子提供者、その家族に地域 みんなに見守られ子育てを
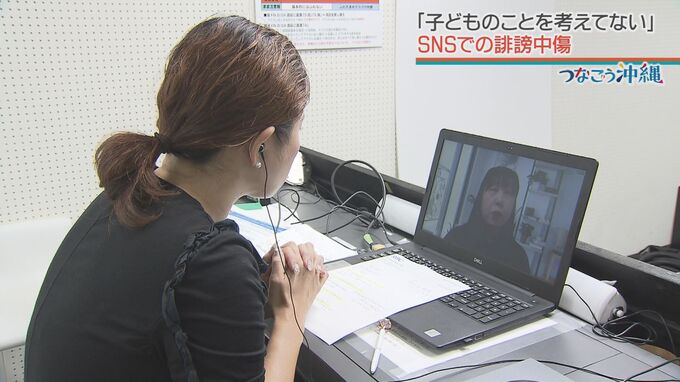
日本では同性カップルが安心して子どもをもつ状況にないと、琉球大学の矢野教授は語ります。
琉球大学法科大学院 矢野恵美教授
「現在34の国と地域では婚姻平等が達成している、というデータがでています。スウェーデンでは、2009年には婚姻平等が達成しました。結婚においての性別の制限がなくなったんです。これで何が起こったかというと、いまレズビアンカップルでお子さんを持っている割合と、異性カップルでお子さんをもっている割合がほぼ同じになりました」
「いろいろな人がいるというのが、当たり前になってくると差別の意識ってなくなると思う。どんな形の家族であっても、子どもに同じ権利が保障される。法制度を作るということがとても大事なことだと思います」
matoさんのパートナーさつきさんは、周りの人のサポートがあるからこそ、いまの生活があると言います。

matoさんのパートナー さつきさん
「ふたりママっていうと、ふたりだけで子育てしてるっていうイメージがついちゃいそうなんですけど、実際はそうじゃなくて。うちの血のつながらない、娘にとっては血のつながらない家族だったり、matoさんのお母さん、お父さん、ご親戚の方々や、もっといえば精子を提供してくれた方のご家族とか、その方とか、地域の方々に見守られながら子育てができていることが、すごく幸せだなって思っていますね」
今後は、同じ境遇のカップルのサポートする環境づくりに取り組みたいと語るmatoさん。Matoさんの活動は、SDGsの目標のひとつ。誰もが生きやすい社会の土台づくりに繋がっています。

matoさんは、男女のカップルだけでなく、多様な家族が当たり前になる未来を願っています。
【記者MEMO】
matoさんは、パートナーとの妊活や子育ての取り組みなどをインスタグラム「#ふふはぐ」で紹介しています。
沖縄県では那覇市と浦添市で同性カップルについての「パートナーシップ制度」が導入されています。また那覇市では、2022年に同性パートナーそれぞれの三親等以内の同居する親族についての「ファミリーシップ制度」も導入されたものの、これらは法的には配偶者や家族とは扱われず権利が認められていません。
法律上、同性婚ができないために求められないことの例として、所得税の配偶者控除・パートナーが亡くなった時の相続、共同で子どもの親権を持つことができない、病院によっては病状や説明を受けることができないなどの弊害も多く存在します。多様性を認める社会に一歩でも近づくことが求められています。