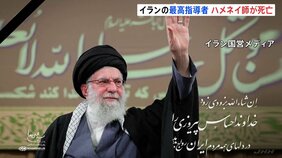高温に強く、独特のもちもちとした食感が特徴の在来種トウモロコシ「もちとうきび」。その魅力を再発見し、普及を目指す取り組みが大分県で進められています。気候変動への対応や地域資源の活用にもつながる昔ながらの作物が今、再び注目を集めています。
井口キャスター:
「トウモロコシの栽培が盛んな戸次地区では、もちとうきびが収穫期を迎えています」

2メートルを超える高さにまで成長したもちとうきび。江戸時代から大分で栽培されてきた伝統的な品種で、もち米のような粘り気のある食感が特徴です。
もちとうきびの魅力に着目し、普及を目指すプロジェクトを進めているのが、大分市の企業「タカフジ」と、大分高専の森田昌孝准教授です。
もちとうきびは長年、農家の自家消費用として栽培されてきましたが、糖度が高いスイートコーンの人気に押され、種の継承が危ぶまれているといいます。

森田准教授:
「大分に来て、在来のトウモロコシに初めて出会いました。研究者としてもすごく珍しいと感じ、経済の中でちゃんと回していかないと種は残っていきません」
今年は栽培面積を拡大し、料理人を招いた意見交換会も実施。もちとうきびの可能性を探っています。
森田准教授:
「甘さや大きさで劣っているので、どんどん減ってきましたが、次世代につなげていきたいという思いで栽培を頑張っています」