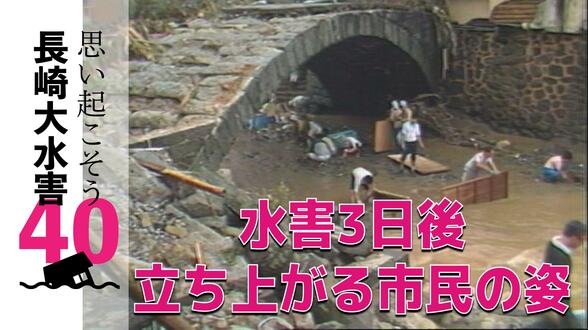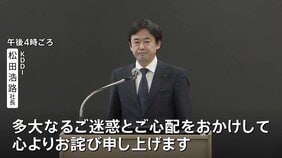2017年の九州北部豪雨やおととしの熊本豪雨などでは、長崎を含む全国の消防から援助隊が出されました。
それでも大規模な災害現場での救助は困難を極めたといいます。
緊急消防援助隊として活動した長崎市消防局 警防課 高橋 啓輔 消防司令補「まずは被災地に着いて実際の救助現場にたどり着くのが困難。瓦礫、土砂、流木など、それをまず排除しないといけない。かなり時間がかかる」
長崎市消防局指令課 吉野 雄介消防司令補「119番をかけるというときには、既に災害が発生しているときであったり命の危険があるというところになるかと思いますので、危険が及ぶ前に避難をしていただきたいと思っております」
長崎市籠町の道野志津子さんは、大水害から40年が経ったいま、この町で民生委員を務めています。

「伊藤さん、元気にしとった?」
「元気、生きています。病院もいった病院も」
道野さんは町内の人たちと一緒に一人暮らし世帯の見守り活動をしています。こうした顔の見える関係づくりが災害時に早めの避難の呼びかけにつながると考えています。
堀上 正子さん「町内のハザードマップとか何とかの確認で、自分の周りに誰と誰を確認すると決めていますから」
伊藤 朝子さん「遠慮なく皆さんにお世話なっていますよ」
道野 志津子さん「私の場合だったら声かけですね。"大丈夫ね?"っていうだけでもね、みんな安心するかなと思って、助けにはいけなくても、声かけて少しでもですね、力になればと思ってます」
災害時に命を守る最後の砦となる消防。
助けを求めるまでに自分たちでできる最善の行動は何かを考えることが、大水害から40年経った今求められています。
長崎市消防局では実際に災害が起こった場合や命の危険がある場合には、ためらわずに119番通報をしてほしいとしています。