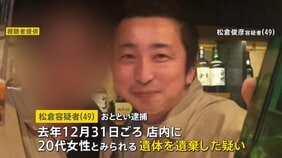説明会に参加した夫婦「子供が欲しい…」
長崎県里親育成センターが里親委託率が低いもう一つの理由として挙げたのが、里親制度の認知度不足でした。
県では制度の理解を深め、2029年度までに委託率を43.2%に上げようと、県内各地で出前講座を行い里親への経済支援や、サポート体制などを紹介しています。
説明会に参加していた1組の夫婦に話を伺うことができました。

県内在住の夫婦:
「子どもがずっと欲しかったんですけどできなくて、自分と血が繋がってなくても一緒に暮らしてみたいなというのがやっぱりずっとあって。職員の方に聞いたら土日とか夏休みとかに(短期間)預かる制度もあるということなので、そういう体験を積み重ねることで勇気を持って踏み出せるのかなと思いました」
伝える?生みの親の話
もともと里親として女の子を受け入れた阿部さんですが、その後特別養子縁組を行い、今は法的にも親子となりました。阿部さんは、女の子に産みの母親がいることも伝えています。

母・千賀子さん:
「『会いたいと思ったら言ってね』という話をしてるんですけど『まだ今はいいかな』と本人も言っていて。でもやっぱり『会いたい』、『やっぱり自分のルーツを知りたい』、そういう時期が来ると思うので、その時はお母さんと会う環境は作ってあげたい」
Q(女の子に)お父さんお母さんのことはどう思ってますか?
「お母さんはいつも料理が美味しくて優しいし、パパも一緒にサッカーに付き合ってくれて優しいです」

母・千賀子さん:
「本当幸せです。子どもたちと過ごすだけで。」
里親として子どもを迎え入れても、その後上手く行かないケースもある里親制度。ミスマッチを減らすためにも、まずは制度の認知度を上げ、希望する大人と子供を結ぶ環境を広げることは欠かせない要素です。
阿部さんは自分たちの家族をひとつのケースとして知ってもらうことで「里親制度」が社会に浸透し、一人でも多くの子どもがそれぞれの幸せを見つけることができることにつながればと話しています。