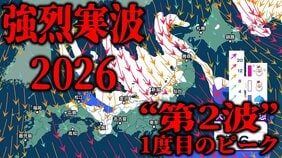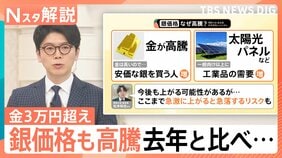〇上下水道復旧も依然使えないトイレ、汚物の袋が破裂し…
奥能登でも、各地で早期復旧困難地区を除いての断水解消の情報が聞かれるようになりました。断水の解消は喜ばしいことですが、それだけですべてが元通りになるわけではありません。下水道にあたる浄化槽の修理は、いまだ順番待ちの状態が続いています。
奥能登はほぼ全域で甚大な被害があり、修理業者の方も被災している中、金沢などから業者の方が入るようになりましたが、様々な理由でトイレが使えていないご自宅や施設はまだ多くあります。
浄化槽が使えないため、簡易トイレや災害用のトイレシートなどで対応を続けている状況です。
一番被害が大きかった時期に比べて少なくなってきたとはいえ、今現在でも汚物が出る地域があるのです。
この簡易トイレは排泄物に凝固剤を入れて処理するのですが、凝固剤といっても完全に固まるわけではありません。
このトイレのゴミは、輪島市ではもえるゴミ扱いとなりますが、ゴミ収集車での回収・圧縮時に破裂し、収集車や作業に当たっているゴミ収集員の方が汚れてしまうということが、多々起きているという話を伺いました。
酷い時はゴミ収集車の後方に、汚物が2〜3メートル飛び散ったこともあり、水が使えない上に、汚物が飛び散ったままの状態で次のゴミステーションに移動しなければならず、ゴミステーション付近が汚物まみれということもあったそうです。
発災当時は冬で、雪や雨で流れましたが、断水のため洗うことも出来ず、どうしようもなかったため、その苦労や心労は計り知れません。
汚物の破裂被害に遭わなくても、汚物が飛び散り、ゴミステーションを汚してしまうため、衛生面だけでなく感染症の問題もありました。
断水が続いている中では、収集車を洗うことも汚れた制服を洗濯することもできません。ゴミの中身がなんであるかわかれば、対策が出来るとのことで、多数の人が避難していた町野町の東陽中学校の避難所では、排泄物の入ったゴミを他のゴミと分けて収集に出すという対応に切り替えたそうです。
対応のおかげで、排泄物のゴミはトラックで別途回収し、排泄物の汚れを避けることができるようになりました。
ただ、この対応に切り替えることができたのは、東陽中学校の避難所だけで、他のゴミステーションは生ゴミと同じ場所に汚物が混在して置かれていました。
やらなかったということではなく、被害が甚大で全員が被災者。指定避難所以外の場所で、住民同士が助け合いながら避難生活を続けるなかでは、「やりようがなかったのではないか」と、お話をお伺いしたゴミ収集員の方はおっしゃっていました。
それでも、避難者の人数が非常に多かった東陽中学校が分別を実施したことで、町野町でのゴミ収集作業時には、かなり助かったそうです。
収集時に「中身が汚物かどうか分からない」ということが、被害の拡大を招いたとのことですので、中身がなんであるかを明示して分別するだけでも、対策になるのではないかと思われます。
ゴミは出したら終わりではなく、それを収集し、運び、処理する方がいらっしゃるということを、災害時にこそ考えなければならないと改めて感じました。
ゴミ収集員の方からは、「早くトイレが普通通りになってほしい」という切実なお声をお伺いいたしました。
本記事をご覧になられているみなさまも、大きな災害時のトイレの処理について今回の発信を機に、もう一度考えていただき、もしもの時、少しでも思い出していただければと思います。