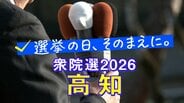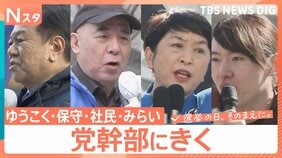「若者に人気」で需要があるから“脱法製品”が出回る…
▼C&H 平野弘樹 研究員
「おそらく、海外の合法的な所に行って、『THC』が医療用途として有効性があると研究されている・がんの治療に役立っているのを現地で見てきて、日本では非常に規制が厳しかったり偏見も強かったり…で“反発”はあるのかな、という印象はありますね。そこに現れているのが『THCに似た成分』。大麻由来の成分が微量でも含まれている『THCH』などに流れていく人が増えているのは、そういった社会的背景もあるのかなという印象はあります」
▼C&H 平野弘樹 研究員
「世界的には『THCはいい側面もある』ことが言われているのに、国内では医療用途の研究が進まない…というところに『反発心』や『THCに類似したものだったら研究結果に近いものが得られるんじゃないか』という“期待”みたいなものを抱く人が、若年層に多い…ということはあり得ると思っています」
▼C&H 岩間洸汰 社長
「『THC類似成分』って、人工的に作ろうと思えばいくらでも“法律の穴”を抜けて作れると思うんですよ。結局、買い手がいるから“いたちごっこ”が発生しているところもあって…。お酒の代わりとして『お酒は飲めないけど、楽しみたい』という人は一定数どうしてもいるので、大麻に限らず、そういうのは存在し続ける」
法律で規制を繰り返しても、実際には規制の穴をくぐり抜けて「別の新たな物質」が流通しているのが現状です。その結果「物質の管理や健康被害の把握が難しくなり、より危険な薬物が蔓延し、問題が複雑になっている」と2人は指摘します。
▼C&H 平野弘樹 研究員
「“いたちごっこ”なんですよね、規制をかけていくこと自体が。“いたちごっこ”で状況が改善されたかというと、あまり改善しなかったんですよ。要は、規制されたとしても別の薬物にいってしまって、それで搬送される人が増えたり、逮捕される人が増えたり…と、状況があまりよくならなかったというのがあります。実際に売る店は無くなったと思うんですけど、『社会全体の状況が良くなったか』と言われると、ちょっと難しいところはあるのかなと…」
こうした上で2人は、類似成分を使った製品を使う人が「法的リスクを負う可能性がある」ことを念頭に置いて、責任を持つべきだと強調します。
▼C&H 平野弘樹 研究員
「『類似成分』となってくると、研究が全然されていなくて安全性もほとんどわかっていない状態なので、透明性が低くなってくる。使う際、製品を試してみたいのであれば『THC類が含まれていない』ことがちゃんと確認されているような製品を試す。そういったことが今後、重要になってくる」
▼C&H 岩間洸汰 社長
「結局、安心・安全の保障は何もないので『購入者の責任』になってしまう側面もある。もちろん、売るのが一番悪いんですけど、自分の買うものに対しての責任は自分で持ってほしい。もしかしたら健康被害につながる可能性も、無きにしもあらずだし、『合法』だと謳われて手に入れた製品でも、包括規制で実はすでに違法になっている可能性もあるんですよね。『法的なリスクも負う可能性がある』ということも、理解しないといけないと思います」