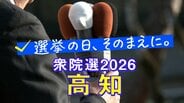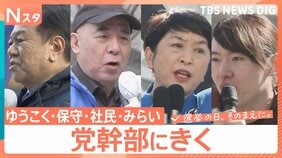「大麻に似た成分」は様々、使った時のリスクは?
京都の同志社大学内で大麻成分の研究を行う民間企業「C&H」の岩間洸汰社長と平野弘樹研究員は、「大麻に似た成分」を「大麻の主要成分=『THC』の類似成分」と定義したうえで、取材に応じました。
大麻の主要成分である「THC=テトラヒドロカンナビノール」は、大麻を使った際にみられる“多幸感”などの精神作用を引き起こす原因物質で、日本では「麻薬及び向精神薬取締法」における「麻薬の1つ」として位置づけられています。
その「THC」に似た化学構造をもつ「THCH」や「THCB」などの物質があります。「THCH」や「THCB」は、当初は法律で規制されておらず“THCの代用品”として扱われていたこともありましたが、大麻由来の成分が含まれているため、現在は法律で規制されています。
しかし、法の目をすり抜けて出回ってしまっているものもあり、それらは危険な不純物や添加物が含まれている可能性があるうえ、そもそも本当に「THCH」や「THCB」なのかどうかも怪しい…といいます。
▼C&H 岩間洸汰 社長
「こうした薬物を使用して、みんなが期待しているのは『ハイ』になることだと思いますね。ただ、実際には、たぶん気持ち悪くなる人も多いだろうし…」
▼C&H 平野弘樹 研究員
「『酩酊作用』や『記憶に対する障害』などのリスクに関わる副作用はあると言われています。『大麻・THCを摂取しすぎると、体内の受容体に過剰に作用するため、副作用が起こる』ということがわかっています。医薬品用途で使われているものは、体内の受容体に対して過剰摂取にならないよう、量をコントロールして“管理されて扱われている”という背景があります」
「記憶に対する障害も発生しうる」という大麻類似成分。近年は規制が厳しくなり、流通も少なくなってきていますが、SNSを通じて個人間でやり取りされている可能性があるほか、規制こそされていないものの安全性が確認できていない薬物を販売している店舗もあるということです。