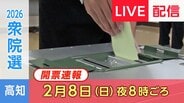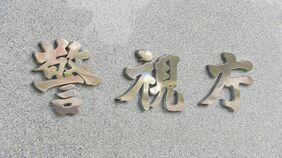いま、「インターネット」が「選挙」に及ぼす影響力が、大きくなっています。なぜ、そうなったのか。そして、有権者である私たちが注意するべきことなどを、専門家に聞きました。
「2024年」は日本の選挙とSNSの“転換点”
■国際大学 GLOCOM 山口真一 准教授
「昨今、SNSや動画共有サービスが、選挙時に非常に大きな影響力を持ってきています」
こう話すのは、SNSやインターネットの特性に詳しい、国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの山口真一准教授です。統計分析手法の1つである「計量経済学」が専門で、SNSなどの社会的な現象について実証研究を行っています。山口准教授は、ネットやSNSが選挙で大きな影響力を持つようになった「分岐点」を、「2024年の東京都知事選と、兵庫県知事選」だと分析しています。
■国際大学 山口真一 准教授
「私は『2024年が、日本におけるSNSと選挙の転換点であった』と考えています。なぜなら、2024年の兵庫県知事選や東京都知事選では、インターネット上で非常に人気となった候補者が、非常に多くの票を得て躍進したからです」
■国際大学 山口真一 准教授
「2024年の兵庫県知事選挙でNHKが投票所で行った出口調査では、『有権者が参考にした情報源』で最も多かったのが「SNSや動画サイト:30%」で、「テレビ:24%」、「新聞が24%」となりました。このように、SNS・動画サイトが『最も参考にする情報源』にまでなっています」

また、2024年10月の衆院選の調査結果をみると、全体では、政治や選挙の情報を「テレビ」で得た人が最も多くなっていますが、2番目に多かったのは「ソーシャルメディアを含むインターネット」で、「新聞」を上回っています。
さらに年代別でみると、18歳~29歳の51.1%、30歳~49歳の44.1%が「インターネット」から情報を得ていて、「若い世代ほどインターネットやSNSを選択している」ことがわかりますが、その傾向は「中高年世代にもみられる」と、山口准教授は分析しています。