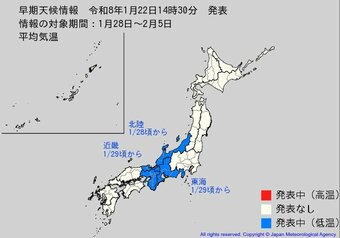“過疎地域”で起こる医療崩壊の危険性
若新雄純 慶応大学特任准教授:
医療崩壊というものが現場で起きつつあるんだと思います。
救済のために、医師が多く現地に駆けつけているが、能登半島の人口はそれほど多くないにも関わらず、住民が住んでるエリアが広く、かつ、薄くまばらなために、小さな避難所があちこちに点在している。1か所に集約されていれば、医療行為も効率的に施すことができるが、あっちにも避難者、こっちにも避難者、向こうの公民館にもお年寄りがいて移動が大変ってなると、医師もぐるぐる回らなければならない。

これは能登半島だけの話ではなくて、日本各地に、人々がまばらに生活してる過疎地域がある。しかし、災害は場所を選ばずに起きる。地方の文化は大切です。それを捨てる必要はないが、いざというときのために、ある程度、地域ごとにまとまって、コンパクトにまちを作っておくことを考えておかないと、また同じことを繰り返しかねない。コンパクトにまとまって文化を育て、残していく、コンパクトシティについて考えるときが来たと感じます。
さくら総合病院 小林豊 院長:
珠洲市を見ていても、30~40人という小さな規模の避難所が各所に点在している。各避難所に医療チームが入って、健康のチェック、環境のチェック、感染管理などをしなければならないが、本当のところを言うと効率が悪い。1か所に集めて管理をする方が楽ではある。

しかし、避難所にいらっしゃる方の多くは、家が全壊したわけではなくて、部分損壊で、昼間は家で過ごすなど、なかなか家から離れたところに避難することが叶わないんです。また、高齢者の方にとっては、住み慣れた家とか、見慣れた景色とかが、実は精神安定剤になる。地元を離れ、順応性が落ちると、高齢者にとってはものすごいストレスになって、うつ病や適応障害、認知症の増悪などを生むので、災害関連疾患を考えると無視できません。