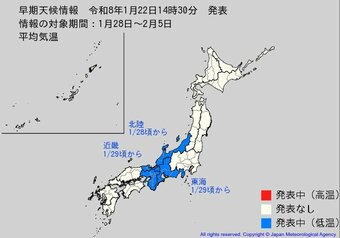支援と情報がマッチするため…“情報の道”は太く正確に
ホラン千秋キャスター:
各自治体が全力で支援が行き届くようにしていると思うんですけれども、やはり自治体によってむらが出てしまう。日比さんは現地で取材をしていましたけれども、この支援が遅れているな、もう少し早くスピード上げられたらいいのになと思う部分は何かありましたか。
日比麻音子キャスター:
物資に関しては、届いているところは届いているんです。ただ、食べるものや食材は届いていても、食べる容器がない、紙皿がない、割り箸がない。そういった具体的に必要なものに関しての情報が届いていない。ですから、より的確な支援・サポートというものがなかなか進んでいないところが多くあるなと思いました。

若新雄純 慶応大学特任准教授:
元々能登半島のこのエリアは、地元の人からしても非常にアクセスが悪く、不便な場所だったんですね。もちろん、物理的な道は元々すごく細く、くねくねした道で復旧・復興に時間がかかるのは当然ですが、こういうときこそ物理的な道だけじゃなくて、情報の道というのをいかに太く正確に繋げるかということが大事だと思います。
今回、石川県も正しい情報を早く正確に一本化して発表するというのはなかなかできなかった。もちろん、「勝手に行くな」とか「勝手に応援に行っても邪魔だ」みたいな議論もあったんですけど、県が公式な発表やボランティアの募集、状況を伝えるのに時間かかり、“正確だけど遅い”という問題があったそうなんです。そうすると現場にいる人から「助けに来て欲しい」「こんなものが欲しい」というのが、各々個別に、ネットを通して届くようになり、混乱したということがあったと思います。
これから同じような災害に見舞われる可能性が高い日本としては、せめて情報の道はすぐ、早く繋がるように、自治体も我々もやはり意識して使えるようにしておく。混乱を招かないためにも、そこは課題だと思います。
日比キャスター:
行政の連絡を待っていては遅いから、もう自分が動くしかないんだという方もいらっしゃいますよね。

ホランキャスター:
各自治体、こうした災害などに備えて、有事の際にどう対処していくかシミュレーションをしていると思います。けれども、それが通用しない場合もあるということを考えると、やはり情報の道を連携して整備していくことは、どの自治体でも必要だなという感じがしますね。
若新雄純さん:
インターネットの情報の道は、誰かがトップで決めて“トップダウン”で決める場合と、みんなで相互に作りながら同時に開発する方法があります。後者にもっと強くなるべきだと思います。