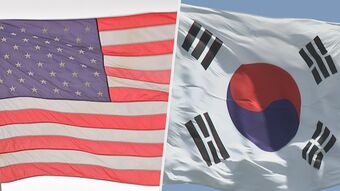大阪入管局長は難民と認定せよ~裁判所は、法廷で本人の発言に耳を傾けて判断した
裁判所の判断は、その過程も結論も、入管庁や参与員とはまったく違っていた。
難民不認定となった女性は大阪地裁に処分の取り消しなどを求めて提訴した。22年10月には、自ら出廷して裁判官に「ウガンダでは同性愛者が自由に生きることはできない」と訴えた。
そして、今年3月、森鍵一裁判長は「難民と認定しない処分を取り消し、大阪入管局長は難民と認定せよ」と命じる判決を言い渡した。
判決文にはその理由が極めて丁寧に書かれている。
欧米政府や国際機関の報告書などを元に、
「ウガンダでは同性愛者への差別意識が強く、警察など国家機関にも残存、刑法や他の法令を適用して逮捕や恣意的な身柄拘束をする可能性がある」
「女性は同性愛者を理由に逮捕され、警官から暴行を受け、重症化するまで相当長期間にわたり適切な治療を受けられないまま拘束された」と認めた。
そのうえで、同性愛者という特定の社会集団の構成員を理由に迫害の恐れがあり難民に該当すると判断した。
被告の国側に対しては、
「『民間団体の報告書に、看過し難い疑義があり、およそ証拠価値はない』という主張は極論」
「供述の変遷を主張するが、中心的な部分について変遷はない」などと退けた。
裁判所が入管と異なる判断をしたことについて、齋藤健法相は参院法務委で「訴訟の過程で(女性の)主張を裏付ける新たなものが出てきて覆ったと理解している」と述べたが、代理人の川﨑真陽弁護士は「たとえ参与員に新資料が提出されていても、不認定の結論に変わりはなかった。答弁は、その場限りのごまかしだ」と指摘する。その通りだと思う。そもそも「真実でも難民と認めない」というのだから、どんな証拠が出てこようと考慮されようがない。
そのうえで川﨑弁護士は「ウガンダのように法律で同性愛を罰している国の場合は、難民と認定しなければならないのに、1次の入管庁も、2次の難民審査参与員もずさんな審査だった。しっかり向き合う姿勢がなかったとしか言いようがない」と語った。
渡辺弁護士は、私の取材にあらためて「出身国がどんな状況にあるのかという情報を一切、見ていないの一言に尽きる」と批判した。
入管法改正案では、3回以上の難民申請者の送還を原則可能にする。これは、難民認定制度が適正に機能していればこその話だ。「難民をほとんど見つけることができません」と国会で断言した参与員の発言に疑問の声が上がるが、保護すべき人がいないのではなく、見逃しているという現実を直視すべきではないか。