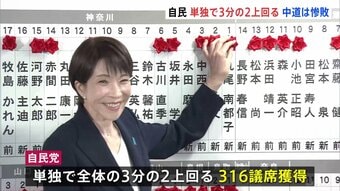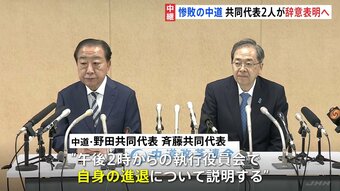■「日本で働きたい」避難民の前に立ちはだかる言葉の壁
幼い頃から日本のアニメや文化にあこがれ、日本に避難したオルガさんは、戦争が終わっても日本で生活していくことを希望している。医師のウラジーミルさん一家も、ふるさとが落ち着くまで数年は日本にいたいと考えている。長期間の安定した生活のためには継続的な収入が欠かせない。避難民の就労に向け国はどう支援するのか。
4月28日、古川法務大臣の会見で「働きたいウクライナ避難民への具体的な支援策と、受け入れ企業に求めることはあるか」尋ねた。
古川法務大臣
「政府としては在留資格の切り替えを特例で認め、就労資格を与えています。これで就労を希望する避難民は働くことができます」
一方、オルガさんは就労資格があっても「日本語ができないと働くのは難しい。コミュニケーションができない」と漏らす。ウラジーミルさんはベーカリーショップでアルバイト体験をしてみたが、作業が書かれた紙や、「塩」「砂糖」「はちみつ」など日本語のラベルを見て、困惑していた。

ウラジーミルさん
「きょうは在日ウクライナ人の店員さんがウクライナ語で教えてくれたけど、彼女がいない時間帯だと一人でできるかどうか」

■取材で見えた課題 「必要な支援」とは
医師だったウラジーミルさん、カフェ店員だったオルガさん。2人とも本心では、日本でもこれまでのキャリアを生かした仕事に就きたいと考えている。しかし、日本で言葉の壁に直面している今、妥協点を探っている。身寄りのない避難民には一時滞在施設で日本語教育などもスタートしたという。
ロシアの侵攻が長期化する中、さらに避難民が日本に来ることが予想される。抱える課題は人によって様々で、各自にニーズにあった支援ができるかどうかがカギだ。身寄りのあるなし、で支援を決めるのではなく、柔軟な姿勢が求められる。