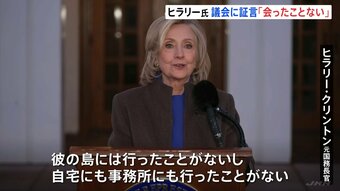3月22日、国連本部でグテーレス事務総長は次のように演説した。
「ウクライナ国民は生き地獄を耐え忍んでいます。そして世界中が影響を受け始めています。食料、エネルギー、肥料の価格が急騰し世界中で飢餓の危機に陥る恐れがあります。戦争が終わるまでに世界でどれほどの人々が飢餓に直面しなければならないのでしょう」
事務総長が警鐘を鳴らす“飢餓の危機”その原因はいうまでもなく、世界有数の穀倉地帯が戦場になっているからだ。三大穀物においてウクライナは世界の小麦の8.4%、大麦の13.8%、トウモロコシの13%を生産している。一方、西側の経済制裁によって物流がままならないロシアもまた小麦の世界シェア19.6%、大麦で15.5%を占めている。また、ひまわり油に至っては、ウクライナとロシアで実に世界の75%をまかなっている。これだけの食糧が、戦争によって世界に出回らなくなっているのだ。
■「ロシアは食料を外交の武器にしている」「これは食料の戦争だ」
ロシアとウクライナの穀物が滞ることの意味について専門家に聞いた。
経済評論家 加谷珪一氏:
両国合わせて小麦だと3割以上になります。この小麦がなくても量としては何とかなるかもしれないですが、ほかの地域の小麦を確保しようと殺到しますから価格が上昇します。小麦が入らなければ、次はトウモロコシ…というように代替品の確保に走ってしまいます。結局のところすべての穀物の値段が上がることになり、国によっては危機になると思います。
ロシアとウクライナの穀物は、食料とは別の危機をもたらすと話すのは、旧ソ連地域を研究する服部氏だ。
ロシアNIS経済研究所 服部倫卓所長:
ウクライナはヨーロッパのパンかごとも言われていますが、実はロシアやウクライナの小麦やトウモロコシはあまり品質が高くない。先進国向けに輸出されているものは基本的に家畜の飼料用です。つまり現在ヨーロッパの人がウクライナの小麦のパンを食べることはないです。しかし途上国、新興国では食料となっていますので、そちらの市場での影響が大きいかと…。
確かに中東・アフリカ地域では、ロシアとウクライナからの小麦依存率50%を超える国が26か国もあり、既に深刻な命の問題になっている。その一方ですでに小麦の国際価格は過去最高値を記録しているが、これは食料危機から値上がりを見込んだ資本家たちの投機の影響も大きいという。しかし生産者側は上がった値の恩恵を受けることはない。番組ではウクライナの農家に直接話を聞いた。