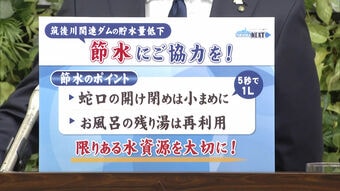消費者物価が示すデフレ圧力
かつて「ダサい、性能が悪い」と悪評だった中国メーカーの自動車は、EVを牽引役に市場を席巻するまでになりましたが、それも一段落しました。そして、不動産バブルの崩壊から始まった内需そのものが低迷しています。
中国政府は昨年秋から、個人消費を押し上げるため、車や家電の買い替えに際して補助金を支給するシステムを開始し、今年は日本円で約6兆3000億円の予算を投じています。しかし、巨大人口の中国といえども、需要には限界があります。
需要が不足すれば、デフレ圧力も強まります。9月の消費者物価指数は、1月から9月までの9か月間で前年同期比0.1%下落しました。特にEVを含む自動車やバイクの価格は競争激化により3.2%低下しており、売り上げが増えても利益が上がらない厳しい状況です。
習主席が号令する「自立自強」の深層
先週の重要会議のコミュニケ(声明)は、向こう5年間の政策方針として、以下のようにうたっています。
「ハイテクノロジーの自立、そして強化を加速し、質の高い生産力を発展させる。ハイテク革命と産業構造転換の歴史的チャンスを捉える」
「自立自強」(他者の力を頼らず、自分自身の力で強くなる)という4文字は、ここ数年、中国の公式文書で頻繁に登場します。これは、「海外に頼らない」――とりわけ科学技術の分野で、この路線を加速させるという習近平主席の号令です。
これは、毛沢東時代に使われたスローガン「自力更生」(自分自身の力で困難から立ち直ること)と似ており、毛沢東のような存在になりたい習主席の執念を感じます。
コミュニケはまた、向こう5年間を「チャンスと共に、リスクが共存し、予測不可能な要素が増す時期」と位置づけ、「強力な国内市場をつくり、中国独自のサプライチェーンも構築しよう」とメッセージを送っています。これは、アメリカのトランプ政権によるハイテク産業への対中輸出規制や関税強化といった逆風に対し、国内で技術開発を急ぐという強い意志の表れです。