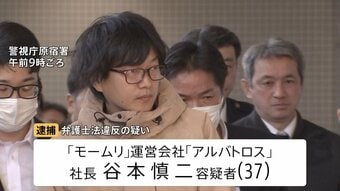大阪・関西万博が10月13日に閉幕した。最終週に行われた高校生による「SDGs未来宣言」と、万博が目指したSDGsとは。「シリーズ SDGsの実践者たち」の第48回。
大阪・関西万博が掲げていた「持続可能な万博」
大阪・関西万博は158の国と地域が参加して、4月13日から10月13日までの184日間、大阪市の人工島「夢洲」で開催された。一般来場者は2557万8986人と発表され、想定していた2820万人には届かなかった。チケット販売枚数は10月13日時点での暫定値で2206万9546枚となっていて、こちらも目標の2300万枚を下回ったものの、一定の経済効果はあったと見られている。


運営面で掲げていたのは「持続可能な万博」だ。主催する2025年日本国際博覧会協会では、万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」に基づいて、「EXPO2025グリーンビジョン」を策定。SDGsが目指す世界観の骨子を構成するPeople(人間)、Prosperity(豊かさ)、Planet(地球)、Peace(平和)、Partnership(パートナーシップ)の「5つのP」に沿った運営を目指してきた。
具体的な取り組みの一つが、省エネルギーや再生可能エネルギーなどの活用による温室効果ガスの削減。会期中の会場内での二酸化炭素排出量を、取り組みをしなかった場合と比較して3万9133トン削減することを目指した。これは約55万本のスギが1年間に吸収する二酸化炭素量に匹敵する。また、会期前後や会場外では、352万4747トンの削減に取り組んだ。

また、廃棄物の発生を抑制するリデュースや、再利用可能な部材を活用するリユースとリサイクルも進めた。会場内で使われた食器は回収してリユースしたほか、ごみについては再資源化するリサイクルにつなげるため、もやすごみからペットボトルのキャップまで、9項目にもわたる分別回収を行なっていた。