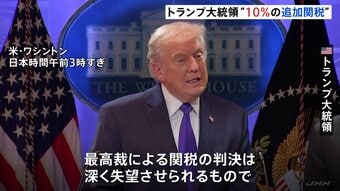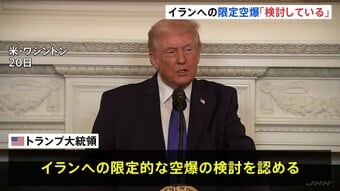■NATOは「国内での核使用」を想定
現在ドイツなどNATOの加盟国に配備されているアメリカの核は「戦術核兵器」だ。大陸間弾道ミサイル(ICBM)などの「戦略核兵器」が敵の本国を直接攻撃できるのに対し、「戦術核兵器」は射程が短く威力も比較的小さいケースが多く、戦場単位での使用が想定されている。では何のために配備されているのか。明海大学の小谷哲男教授(安全保障が専門)は、NATOの核シェアリングは「防衛」を意識した概念だと指摘する。たとえば、冷戦時代の西ドイツがソ連の侵攻を受けた場合、西ドイツに侵入したソ連軍の部隊に反撃しせん滅するために使うというような想定だという。
小谷教授は「これをそのまま日本にあてはめると、例えば南西諸島が中国の人民解放軍によって侵略された場合に自衛隊がアメリカの核で応戦するというような概念だ」と解説する。つまり日本の領土内で核兵器を使うということを意味する。ただ、小谷教授は「今の防衛力の現状を考えれば国内で核を使う必要はないと思う。仮に日本国内に核を置くということになれば逆に敵国からそこが先制攻撃を受けてしまうことにもなりかねない」と違和感を口にした。
■「馬鹿げた非現実的な議論」
防衛政策に精通する自民党の議員も「核シェアリング」をめぐる議論をこう切って捨てる。「馬鹿げていますよ。そもそも、日本が戦術核兵器を使う機会なんてないですよ。非現実的な議論です」(防衛政策に詳しい自民党議員)
それでは、なぜ安倍氏は「核シェアリング」に言及したのか。政府関係者はこんな見方をしている。
「安倍さんだって、いまの日本の制度でできるとは思ってないでしょ。ただ、ウクライナ情勢を日本にうつしてみると、核兵器所有国とのアライアンス(同盟)をいかに強めていくかしかないと思う。そういうなかでの議論ということだ」(政府関係者)
■「非核三原則で国民は守れる。しかし・・・」
一方、岸田総理は国会で核シェアリングについて「非核三原則を堅持している立場から認められない」と明言。「政府として議論することは考えていない」と繰り返している。3月3日の会見では記者から「非核三原則で国民の命が守れるのか」と問われ「国民の命と暮らしを守れると信じております」と断言して見せた。ただ、その後、こう留保をつけた。
「しかし、状況は変化する。技術は変化する。手をこまねいて何もしないわけにはいかない」
ロシアへのウクライナ侵攻によって揺さぶられる国際秩序。そのなかで、何を守り、何を変えていくのか、日本の安全保障政策も選択を迫られている。
TBS報道局政治部 与党担当