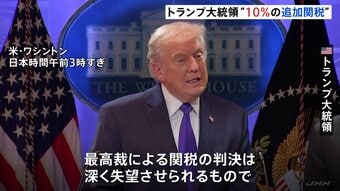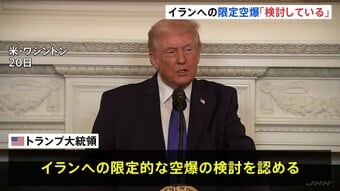■ウクライナ危機で一変 非核三原則の見直し論も
たとえば自民党の世耕弘成参院幹事長。非核三原則を堅持するという政府の姿勢は支持するとしつつも「それでしっかり今後も未来永劫やっていけるのか議論をする必要があるんじゃないでしょうか」と指摘した。日本維新の会も「核シェアリング」についての議論の開始を求める提言を林外務大臣あてに提出した。最終的には削除されたものの、当初の提言案では非核三原則の見直しについての議論も求めていた。堰を切ったように始まった核をめぐる議論。ウクライナ危機の前と後で、政界の議論の風向きは一変した。
日本維新の会の松井一郎代表はこう訴える。「核保有国の大国が他国の領土に入って、一般人も死んでいるわけでしょ。それを目の前に見て、侵略されないようにどうするのか考えないとダメなんじゃないの」
一方で、違う「現実」を見ている人もいる。
■順序が違う?安倍元総理の議論
ある自民党の閣僚経験者は活発になる「核シェアリング」をめぐる議論を苦々しい思いで見ている。「まずは、今の自衛力のままで、どこまでのことができるのかを検討すべきだ」
核兵器の共有によって抑止力を高めることを考える前に、まずは通常兵器の範囲でいかに抑止力を高めるかを検討すべきだというのだ。
たとえば岸田総理が検討を指示しているいわゆる“敵基地攻撃能力”。通常兵器で敵のミサイル基地などを叩く能力を保持することで、抑止力を高めるというものだ。今まさに進んでいるこうした議論をすっ飛ばして「核シェアリング」の議論を行うのは順序が違う、党内にはそんな見方もあるのだ。さらにNATOの核シェアリングは、「日米同盟にはあまりフィットしない概念」(明海大学・小谷哲男教授)との指摘もある。