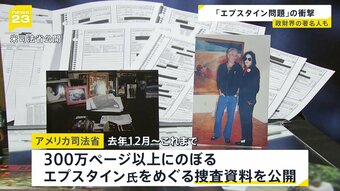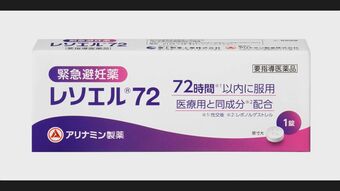チューリップテレビとコラボして実施した取り組み
チューリップテレビと聞くと、2016年に全国的に話題となった政務活動費問題に切り込んだ映画「はりぼて」のことを思い出す読者もいよう。前任校の金沢大学の法科大学院に非常勤講師として長く勤めている筆者は、政務活動費問題の頃からチューリップテレビとつきあいがある。
今回の参院選でのコラボは、筆者のアイデアにチューリップテレビが協力する形となったが、働きかけのきっかけとなったのは実はチューリップテレビ側の取材であった。
チューリップテレビは、2024年衆議院選挙の際、富山1区選出の現職・田畑裕明候補による幽霊党員疑惑を掴んでいながら選挙期間中の報道を見送った(「『紹介者は死亡、党費は知人が…』覚えがないのに自民 “幽霊党員” 富山市連が回答も詳細は非公表 一部議員は『背景含め調査すべき』富山」TBS NEWS DIG)。取材は、その判断が適切だったのか検証する報道特別番組「崖縁 幽霊党員と選挙報道(2025年5月31日放送)」制作のためのものだった。
社会的に、マスメディアには政治家の疑惑を追及することが求められている。しかし、日本のテレビ局は公平・公正な報道が求められる。「崖縁」は、接戦の状況下で選挙結果に影響を及ぼしかねない疑惑を報道すべきかの苦悩が伝わる内容だった。
そうしたこともあり、チューリップテレビ内部でも「何かしなければならない」という雰囲気は感じられたが、やはり何をすればよいのか、難しい状況を抱えていた。加えて、参院選直前に高岡市長選(2025年6月29日投開票)もあり、やれることは限られていた。
チューリップテレビと筆者がコラボした取り組みは、基本的に次の2つである。
ひとつは「素材はWEBに」である。そもそもテレビ局が電波に乗せて伝えている情報は、取材したもの(テレビ局で「素材」と呼ばれる)を切り取って伝えている。テレビという仕組み上、これは仕方がないことであるが、しかしこれは、しばしば「切り取り」と批判されることになる。
「素材はWEBに」は、たとえば、選挙争点ひとつにつき5分などといった形で時間を区切って候補者インタビューを行い、夕方のニュースではそれらのダイジェストを報道するが、局のWEBサイトにはインタビューを素材ごとほぼ全てを載せるという方法である。
この手法のメリットは、陣営からの切り取り批判を回避できるだけではなく、話の文脈も視聴者が(追加的に)理解できることが可能な点である。テレビの選挙報道は時間的制約がある。WEBと連動させて伝えられる情報を増やすという視点を加えることによって、より多くの情報を提供できると目論んだのである。
それだけではない。ローカル局の中には番組で流した映像はストックとして保管しているが、コスト面から番組素材を残していないという局は少なくないのではないか。WEBに流した素材映像を残すことでファクトチェックにも使えるだろうし、次の選挙での現職候補の業績検証にも使うことができるだろう。この取り組みは、高岡市長選挙で実験的に実施し、参議院選挙でも試みた。
もうひとつは、「選挙のトリビアのストックづくり」である(なお、この取り組みは筆者が番組審議会委員を務めているミヤギテレビでも実施した)。
選挙のトリビアを選挙期間中に報道する取り組みは、NHKが先んじており、18歳に選挙権年齢を引き下げた頃から放送やWEBで目にする機会も多い。近年は障がい者の方の選挙に役立つサイト「みんなの選挙(「障害のあるひとの選挙の投票に役立つ情報まとめ みんなの選挙 NHK」)が立ち上がっている。
しかし、全国的に対応でき、選挙プロジェクトチームを構築できるNHKと異なり、ローカル局では公選法に詳しい人材を局内で育てることは容易ではないし、地元に選挙制度に精通した有識者はいないというところも少なくない。
ただ、「気仙沼の漁師さん達の要望が洋上投票を生んだ」「選挙公報がネット上に載るようになったのは東日本大震災がきっかけ」など、選挙トリビアにご当地ネタは意外に多い。
そこで、チューリップテレビでは、筆者を教師役、アナウンサーを生徒役として「選挙のハテナなるほどゼミ」と題したコーナーを「ニュース6(平日午後6時15分~7時)」でつくり、計4回放送した。内容は下記の通りである。
7月7日 (月) 投票箱が家の近くに(移動期日前投票)
7月11日 (金) 2馬力選挙何が問題?
7月16日 (水) インターネット投票なぜ実現しない?
7月17日 (金) 戸別訪問禁止は“ガラパゴス”?
前述の通り、富山でも国民民主党が躍進し選挙区で議席を確認したこともあり、収録した項目全てを流せた訳ではない。ただ、秋には高岡市議会議員選挙が予定されるなど、選挙が参院選後も予定されていることもあり、今後、機会があれば収録済みでまだ流していないものを放送する予定でいる。
このような選挙のトリビアのコーナーをローカル局がつくるメリットは、どのような意義があるか。
考えられるメリットのひとつは、選挙制度は基本的に頻繁に変わることはないので、ストックとしておけば、1年から2年の間、選挙のたびに再放送できる、である。また、近県の系列局と動画を共有できれば、取材コストを抑えることもできる(共同制作としておけば、権利関係も容易にクリアできるだろう)。
ローカル局のストックと考えるだけではなく、地方自治体が行う主権者教育に活用してもらうという手も将来的には考えられる。
筆者は、宮城県明るい選挙推進協議会の委員をしているが、2016年の選挙権年齢の引き下げに合わせてスタートした主権者教育も10年近く経過し内容のバリエーションを増やすことが迫られている。ローカル局が作成した選挙トリビアに関する動画を選挙管理委員会・学校に提供し使用してもらえば、ローカル局にとっては地域貢献したという評価が得られるというメリットが、選管や学校にとっても主権者教育の多様化につながるというメリットが得られるだろう。
できることから挑戦してみる
長い歴史があり、制度的な制約などさまざまな要因もあり、選挙報道を一から大胆に変えることは難しい。ただ、一般の人々が動画を簡単にアップできる時代になり、映像を独占的に配信できたローカル局の選挙報道が曲がり角にあることは間違いない。
NHKやキー局に比べ、予算も人材も限られているローカル局は知恵を絞るしかない。ただ、どこかの局がいわゆる「ファースト・ペンギン」になれば、全国一律の制度を敷いている日本という国では、たちどころにコピーされた(そして地元に合わせてマイナー・バージョンアップされた)取り組みが拡がるだろう。
SNSが選挙に影響を及ぼす時代になる中、ローカル局は何が自らのストロングポイントなのか棚卸しをし、筆者らが行ったように、新しい取り組みに踏み込んでいくべきだと思う。
〈執筆者略歴〉
河村 和徳(かわむら・かずのり)
1971年静岡県生まれ。
慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程を単位取得退学後、慶應義塾大学法学部専任講師(有期)、金沢大学法学部助教授、東北大学大学院情報科学研究科准教授を経て、2025年4月より拓殖大学政経学部教授。
専門は政治学、日本政治論。東日本大震災以降、被災地における政治・行政の分析や、電子投票など選挙ガバナンスの課題などに力を入れて研究を行っている。
著書に「電子投票と日本の選挙ガバナンス(慶應義塾大学出版会、2021年)」など。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。