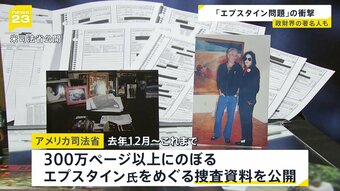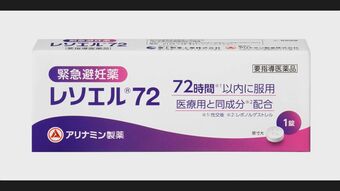難しいファクトチェック
本シリーズの第3回「各局アンケートで大半が『選挙報道見直すべく検討中』~SNS全盛時代のテレビの選挙報道を考える(3)~」で指摘されているように、時代の変化を受け、テレビ局は選挙報道のあり方を見直さざるをえない状況にある。
ただ、見直さなければならないのはわかっているが、何に取り組むべきか、そしてどう取り組むべきか、各局とも悩んでいるように見えた。
今回の参院選で目立ったのは、ファクトチェックの強化である。ネット上に流れている一般の有権者には真偽不明と思われる情報をセレクトし、それが正しいかチェックし解説を含めて報道するのである。
筆者も、日本新聞協会加盟の有志4社(読売新聞社・佐賀新聞社・時事通信社・日本テレビ放送網)の取り組みなどに協力した(「【ファクトチェック】選挙の開票前なのに午後8時に当確が出るのはおかしい?」読売新聞オンライン・2025年6月26日)。
ただ、ファクトチェックの実施は「言うは易く行うは難し」である。容易に偽情報を作成でき、偽情報・誤情報が簡単に拡散できる時代になった今、全ての情報をファクトチェックすることは困難である。
6月に行われた韓国大統領選挙では、韓国中央選挙管理委員会は最新技術を導入し、企業を巻き込みながら多くの人員を割いてファクトチェックを実施したという(高選圭「2025年韓国の大統領選挙におけるSNS・AI選挙取り締まりと日本への示唆」『月刊選挙』2025年8月号)。しかし、中央選挙管理委員会なき日本(注)では、韓国のように人と予算を選挙管理にまわすことはできない。
(注)日本の中央にある選挙管理機関は、比例選挙などに関する事務の管理を行う「中央選挙管理会」
マスメディアもファクトチェックにかけられる資源は限られている。プラットフォーマーでもさじを投げる(「米メタ 第三者ファクトチェック廃止 トランプ氏就任踏まえたか」NHK・2025年1月8日)ファクトチェックをするとなると、どれかに絞らざるをえないし、限られた人員をどう手当てするか、判断する必要に迫られる。
広告料収入が低下し、経営が苦しいローカル局ほど、ファクトチェックに取り組むことは困難であろう。実際、筆者の知り合いの、あるローカル局のトップは、「(もしファクトチェックなどをするとなると、)隣県の系列局でまとまって対応するか、競争相手である県内民放各社で協力体制をしかないと難しい」と述べていた。
国民民主党・参政党の躍進に助けられた?ローカルメディア
選挙区が全県となる参院選や知事選は、選挙区の広さから選挙運動が最も長く設定されているが、現職や既成政党が圧倒的に強いと盛り上がりに欠ける低調な選挙戦になりやすい。そして筆者の経験から言えば、ローカル局は、白熱していれば刻々と変わる選挙情勢をお茶の間に伝えればよいが、盛り上がりに欠ける選挙となるとネタ探しに苦労することになる。
参院選は、新たな取り組みを試すよい機会だったが、上述の通り、何をしたらよいか、考えあぐねているローカル局にとって、国民民主党・参政党の躍進は新しい取り組みを先送りする状況を生んだ。両党の躍進の背景だけではなく、参政党のSNS戦略の巧みさなどを報道する必要が生じ、従来のスタイルでも十分ニュースが埋まったからである。
とりわけ、参政党の「日本人ファースト」という訴えは、選挙前には想定されていなかった「移民」や「治安」といった新しい対立争点を生み出し、外国人労働者を多く抱えている地域では選挙結果にもつながる事態にまで発展した(『読売新聞(群馬県版)2025年7月24日』「[検証 参院選2025]勝者はどこに(下)参政 東毛中心に優位=群馬」)。
そうした状況下であったが、筆者は、この参院選で富山県のチューリップテレビと共同でローカル局ができる新しい取り組みを2つ試みた。どのようなことを行ったのか、以下、紹介することにしたい。