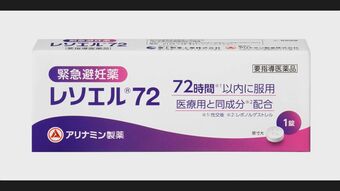SNSを活用した選挙活動への注目が集まる中、7月の参院選でテレビ各局は従来の姿勢を見直すなどして選挙報道に臨んだ。“選挙報道を考える”本シリーズの初回で提言を寄せてくれた拓殖大学政経学部の河村和徳教授が、今回の選挙で関わったあるローカルテレビ局の取り組みについて紹介する。
SNS選挙運動とマスメディア
衆議院議員東京15区補欠選挙、東京都知事選挙、衆議院総選挙、兵庫県知事選挙…2024年はSNSが選挙に強く影響する時代が到来したことを印象づけた。
「新聞やラジオ、テレビといったオールドメディアがSNSに敗北した」という極端な意見を主張する者もいるが、筆者はそうした勝ち負け論に与するつもりはない。
なぜなら、公用語が日本語ひとつで識字率の高い日本では、言語による情報で選挙を認識する長い積み重ねがあり、新聞やラジオ、テレビが選挙情報収集の一翼を担ってきた。その長い歴史にSNSという情報源が加わったということに過ぎない。
SNSで共有される動画(非言語情報)が選挙に与えるインパクトは、識字率が低く、他民族・多言語諸国の選挙に与えるそれほど強くはないと思われる。
また、さまざまな流行と同様、SNSによる小さなバズりをマスメディアが報道することで拡散させ、全国区にする効果は健在である。
その象徴が、2025年参院選における外国人問題の争点化である。参政党が公約で「日本人ファースト」を訴え、それはマスメディアの報道によって全国争点化していった。報道することによって、その情報が有権者に「大事な情報である」と認識させる、いわゆる議題設定(アジェンダ・セッティング)機能がマスメディアにはある。
すなわち、SNSとマスメディアは二項対立の関係ではなく、SNS選挙運動はマスメディアと関わることでより大きな効果が得られる状況にあると考えるべきである。そのように考えれば、東京都知事選で旋風を巻き起こした石丸伸二氏が代表を務める「再生の道」の得票が、思った以上に伸びなかったことにも合点がいく。
ただ、一般の有権者だけではなく、海外の政治勢力も含め、動画情報を広く配信できるようになったSNS時代は、テレビ局、とりわけローカルテレビ局が映像を流す特権を失った時代、と評することができる。一般の視聴者が流せる風景を撮り、「今回の選挙では○○さんが立候補しています」というアナウンスをする選挙ニュース以上のものを視聴者に伝えなければならない時代に転換したと考えるべきである。