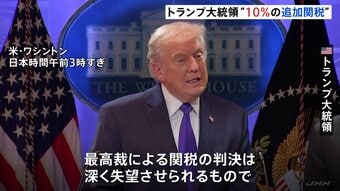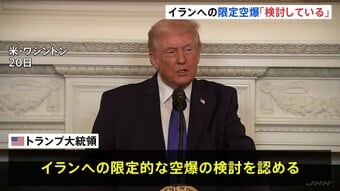■人の脳をコントロールするのが「制脳権」
防衛省・防衛研究所の飯田将史室長(地域研究部 米欧ロシア研究室)は「人間の認識・認知、つまり人の脳をコントロールするのが制脳権」だと解説し「情報の中には意図を持った情報がある可能性があることを意識しなければならない」と警告する。
そして、「SNSなどの新しいメディア空間が誕生したことで、従来の情報戦やプロパガンダがこれまでよりも大きな効果を生む状況が生まれてきた」と指摘する。
こうした中で、この「制脳権」に力を入れているのが中国だと話す。
中国では「認知領域」を「物理領域」と「情報領域」に並ぶ、戦争における三大作戦領域の一つとしてとらえる見方が一般的だ。
中国は軍備を拡大すると共に「世論誘導」や「心理戦」を重要な戦略と位置付けていて、去年、飯田氏がまとめたレポートでは、中国が目指す将来の認知領域での戦いについて、「敵人の脳を支配する『制脳権』の奪取を目的とした『制脳作戦』が将来の戦争における新たな姿として想定される」と指摘している。
また、自衛隊幹部は「サイバーで相手の能力を無力化し、都市を火力で落とす、それと同時に情報戦、メディア戦も展開しないと勝利は導けない」と、従来の戦い方とは明らかに変わってきたと話し、「制脳権」をいかに握るかが勝敗を左右するようになってきたと明かす。
■市民も「兵器」になる可能性
日頃、何気なく気になった動画やニュースに「いいね」を押すことはないだろうか。それは1つのSNSの楽しみ方ではあるが、それが紛争に関わるものであれば意図せずとも市民が情報戦の「兵器」として利用されることになる可能性もある。
「戦争の最初の犠牲者は真実である」とも言われている。フェイクニュースを流し、信じ込ませることは戦時の常套手段でもあるからだ。
人は信じたいものを信じる「確証バイアス」に陥りがちだ。遠く離れた地で起きている紛争でも、SNSを通じ誰もがリアルタイムに生の情報に接することが出来るようになった時代だからこそ、その背景に何らかの政治的・軍事的意図がないのかを考え、拡散する前に一度立ち止まることが私達に求められる最低限の責任だろう。
TBSテレビ政治部デスク 中島哲平