マインクラフトの世界は平等
――子どもたちはすぐに楽しんで進みますが、大人は失敗を恐れたり、振る舞いに悩んだりします。
タツナミシュウイチ氏:
失敗を心配している先生たちは確かにいる。子どもたちはマイクラのプロフェッショナル、先生は教育のプロフェッショナルです。お互いの良いところを発揮し合うのがマインクラフトのワールドです。大人も子どもも同じアバターで平等です。お互いの特技をシェアできるのが、マインクラフトのマインド。詳しくなくても大丈夫です。先生は子どもたちから操作を学び、世の中や科学、歴史を教える。協力して作ることで授業は円滑に進みます。
マイクロソフトの中では、大人やこども関係なく動くことができる。足が不自由な人でも飛び跳ねられる。他の子と同じように活動できる。身体にハンデがある子も、言葉が出にくい子も、平等に活動できるのがマインクラフトのメリットとして先生がタイにもみていただきたい。
年齢や性別、人種を越えた平等な世界がそこにはあると思う。
――画面を見ながら、もどかしさやドキドキを感じる。
タツナミシュウイチ氏:
コミュニケーションが生まれます。それが楽しいです。
――続いてお話しいただくテーマは何番でしょうか。
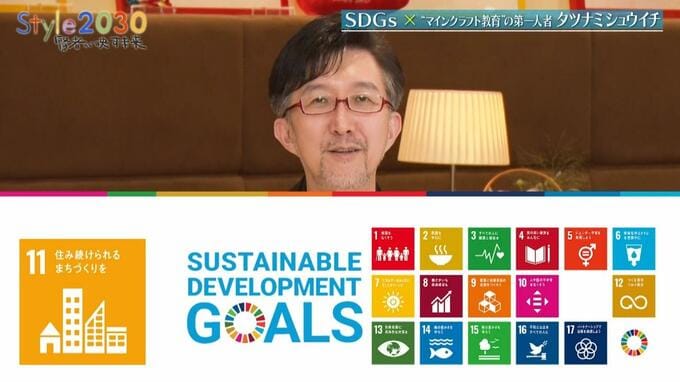
タツナミシュウイチ氏:
11番の「住み続けられるまち作り」です。
――世界作りに挑戦するマインクラフトですから、建物作りに関連しますね。SDGsの11番「住み続けられるまち作り」に向けた提言をお願いします。
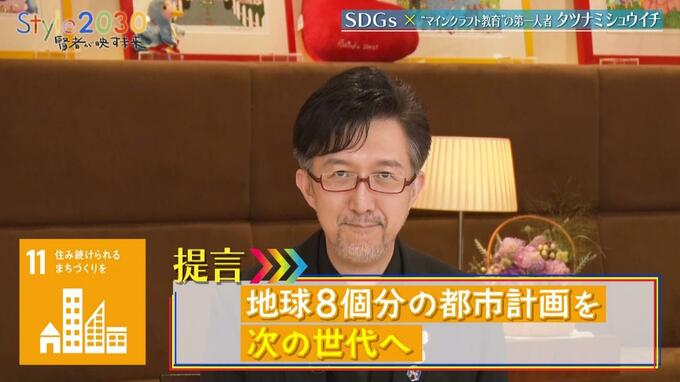
タツナミシュウイチ氏:
地球8個分の都市計画を次の世代へ。
――どういうことでしょうか。
タツナミシュウイチ氏:
マインクラフトのワールドの最大範囲は地球8個分の面積に相当します。理論上、その広さまで作れます。過去、現在、未来の地球を再現しても余裕があります。自分たちの街を作るのは小さな話です。
地域活性化のアイデアをマインクラフトで提案

タツナミシュウイチ氏:
福井県で高校生たちが「デジタル帰宅部」という取り組みをマインクラフトで行っています。三国港や東尋坊、丸岡城など、観光客が減り、盛り上がりがなくなった地域を何とかしたいという自治体の思いがあります。マインクラフトが好きな高校生たちがカフェやバンジージャンプのアイディアを出し、どんどんワールド内で作ります。それを坂井市長にプレゼンすると、「面白いから来年お金を出してやろう」となり、実際に古い建物をカフェに改装し、高校生が店員として働くプロジェクトが始まっています。彼らのアイディアが地元のために広がっているのです。余裕で受け入れてくれる広さがあるのがマイクロソフト。
――その広さ感は大事ですね。
タツナミシュウイチ氏:
地球の大きさの図面は書けませんが、マインクラフトなら再現できます。新しく作り出すことが大きな魅力です。調べることで学びになり、地元の歴史や大切なものを再発見する機会にもなります。














