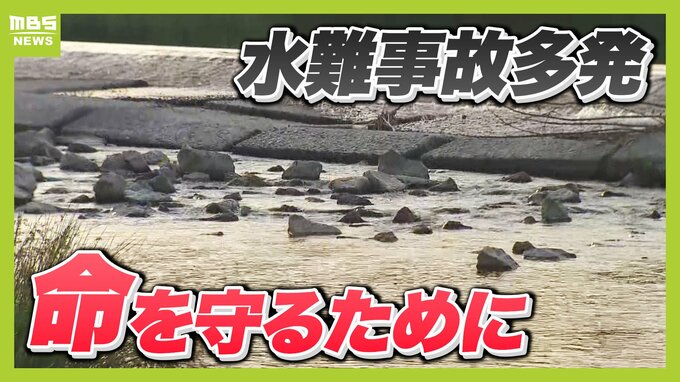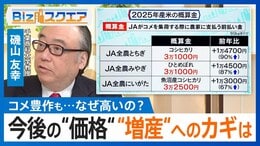いよいよ夏休みのシーズンに入りますが、今年も「水の事故」が各地で相次いでいます。川や海などで命を落とさないために、どんな意識や行動が求められるのか? 長岡技術科学大学教授で、一般社団法人水難学会理事の斎藤秀俊さんに聞きました。
水深は「ひざより上は注意信号。腰より上は赤信号」
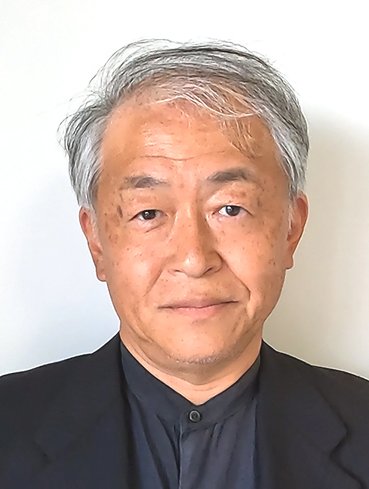
Q 子どもの水難事故、これはやはり親が目を離した間に起きるケースが多いのでしょうか?
「いえ、我々は『放課後水難』と言っていますが、放課後に起きる水難事故、だから平日が多いですよね。学校でいろいろ話をして、『今日の放課後にどこ行く?』という話になった時に、川や海が選択肢としてやっぱり出てくるわけです。そこで事故になってしまうということですよね」
Q 子どもが川遊びなどをする際に、安全な水深はどれくらいと考えればいいのでしょうか?
「ひざ下ぐらいまでの水深で遊んでいれば、基本的には事故に遭わなくて済むということになります。川でも海でも、溺れる原因が何かと言うと、要するに“足のつかない所に、はまってしまった”ということなんです。自由が奪われるような水深、そういう場所には絶対に入り込まないというのが第一の鉄則です」
Q ひざより上ぐらいの深さだと、かなり危険と考えた方がいいでしょうか?
「そういうことです。『ひざよりも上なら注意信号。腰よりも上なら赤信号』と覚えておいてもらうといいと思います」
飛び石など河川構造物の下流側は「思ったよりも深い」

今年6月には兵庫県姫路市の夢前川で、飛び石を渡って遊んでいた男子中学生が川に転落。警察や消防が捜索したところ、飛び石のすぐ近くの水中(深さ2m以上とみられる)で男子中学生が見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されるという痛ましい事故が起きました。
Q 中学生が飛び石を渡っている時に川に転落し死亡するという事故が起きました。やはり河川構造物の近くは危険だと認識したほうがいいのでしょうか?
「一言で言うと深くなっているんです。河川構造物のちょっと下流側というのは『洗掘(せんくつ)』という現象が起き、思ったよりも川底が深くえぐられているんですね。そこが事故のポイントになります。
上流側の水深が比較的浅い構造物のところで遊んでいて、偶然下流側に足を踏み入れたり、すべって落ちてしまったりして、構造物のすぐ下流の深みにはまってしまうという事故が散見されますね。今年は結構それが多いと思いますね。
水深が急に深くなっていることが、子どもも大人もすぐに判断できないんですね。せいぜい腰ぐらいの高さだろうと思って入ったら、思いのほか深くて、体全部が浸かってしまって、そのまま浮かんでこないという事故が構造物の近くではよく起きます」