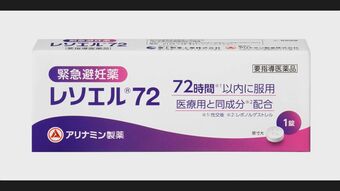失われる「期限付きの自由」 迫る中国の影、危機感を持った香港人
デモの発端は2018年に台湾で起きた、殺人事件だった。香港人の男が台湾で交際相手の香港人女性を殺害。台湾当局は香港に逃げ帰った男の身柄の引き渡しを香港当局に要請したが、香港と台湾の間に犯罪者引き渡し協定がなかったため実現しなかった。そこで2019年2月、香港政府は犯罪容疑者を中国本土や台湾、マカオへ引き渡すことを可能にする「逃亡犯条例」の改正案を提案する。
しかし、香港人は「この法律によって中国に対し批判的な考えを持つ人が中国当局に引き渡され、裁判にかけられるのではないか?」という疑念を抱く。彼らがこうした考えを持つに至るのには、ある伏線があった。

イギリスの植民地だった香港は1997年7月1日、中国に返還された。その際50年間、つまり2047年まで中国は香港に対し「高度な自治を保障する」という条件がつけられた。「1国2制度」である。香港はいまも中国の特別行政区という位置付けで、独自の議会や政府、司法制度をもっている。「中国でありながら中国ではない」といわれるゆえんである。
返還後の香港はいわば「期限付きの自由」を認められていたはずだった。しかし状況は一変する。2014年、中国政府は香港行政長官選挙について「中国共産党が事前に候補者を選定する」制度を導入するなど露骨な介入が始まった。こうした中国の介入に反発し、学生を中心とした市民によって行われたのが「雨傘運動」である。

しかし、「雨傘運動」は失敗に終わり、デモのリーダーたちは次々と逮捕された。香港人は中国の影が徐々に忍び寄ってくるのを肌で感じていた。「香港の独自性を守らなければならない」。こうした危機感が、香港人700万人のうち実に200万人が参加したといわれる2019年の民主化デモにつながっていく。
火炎瓶や投石も...過激化したデモ その結末は
2019年9月末。再び香港を訪れた私が目にしたのは変質したデモ隊の姿だった。6月の段階では幹線道路を占拠しながらも人々は平和的にデモを行っていた。それから3か月。デモ隊は警察に火炎瓶を投げたり、中国系のレストランや企業のガラスを割ったり、信号機を破壊するなど明らかに過激化していた。これに香港警察も激しく応戦。青く着色した液体をデモ隊に向けて放水したり、催涙弾を水平発射したりするなど身の危険を感じるほど現場は激しさを増していた。

ここまでデモ隊が過激化したのには理由がある。デモの合言葉はブルース・リーの名言「BE WATER(水のようにあれ)」。つまり、水がその形を変え、自由に流れるように、特定のリーダーをつくらず、SNSを駆使しながら自然発生的にデモを発生させることで警察に的を絞らせないようにしていたのだ。この手法が奏功し運動は拡大したが、一方でリーダーが不在だったことから運動は明らかにその出口や目的を見失っていた。一部のデモ隊はデモのためのデモに走り、さらに過激化していった。その姿に、当初デモを支持していた香港市民の心は徐々に離れていった。

2020年。新型コロナウイルスの感染拡大を機に、デモの火は消えていった。世界の関心も私の関心も徐々に香港から遠のき、コロナで混乱する世界に向き合うことで精一杯になっていった。