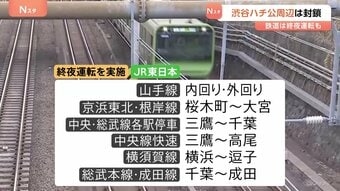“ネック”をどう克服する? 小泉大臣「ありがたいお声が寄せられた」
小泉農水大臣:
今回まず随契の対象として大手の小売さんを対象としたのは、まさに野田代表が御指摘をされた点をクリアして、スピーディーに店頭に並べることができる。この能力を持っているからだと私は理解をしています。
来週、棚に並ぶという事業者におかれては、自分たちのグループで精米会社を持っていたり、そして袋については、既存の袋で対応して、シールで備蓄米という形で張る形でやっていく、こういったことをもって新たなパッケージングが必要ないと。こういった対応をされるところもあるというふうにも聞いております。
そして、精米については、昨日大変ありがたいお声が寄せられまして、日本酒の業界の方からですね、実は今、日本酒の酒米を精米をするところががら空きだと。そこの部分を活用できる余力があるから、具体的に協力の申出をしたいと。こういったお声をいただいて、今、農水省と、日本酒の業界の方と、今お話をさせていただいてるところでもあります。
こういった世の中にあるこのストックの中でも空いているところの活用というのを、農水省とこれから随意契約で結んでいくところのマッチングなども含めてやっていくことは一つ効果があるのではないかなと思っております。そしてあさってから始めていく町のお米屋さんと中小スーパーに対する随意契約、この中で特に町のお米屋さんについては、店頭に精米機をお持ちですので、今回国の備蓄米を精米せず、この玄米のまま店頭にお持ちをすることも出来ます。ですので、様々な形を検討しながら、スピード感を持って、そしてできる限り、広く地域に、この2000円もしくは1800円、備蓄米が行き渡るような努力を続けていきたいと考えております。
野田代表:
私もですね、玄米をストレートに小売にお渡しするようなやり方も可能ならばね、やっぱりやったほうがいいのではないか。それだけやっぱり短縮出来ますんでね。ということはぜひ御検討いただければというふうに思います。
それからですね、備蓄米ってのは国有財産ではありますけれども、こども食堂などへは無償提供が行われてるんですね。これは私は意義のあることだと思う。そのね、無償提供というのを拡大することが出来ないかどうかをちょっと今日はぜひ、提案をしたいと思いますので、御検討いただければと思うんです。
一つはですね、4月から、学校給食用の米価が大幅な値上げがありました。学校給食っていうのは、今保護者が負担をしてますよね。保護者、大体小中学校で、毎年、年単位で5万円ぐらいかかっています。この5万円の保護者の負担を増やすわけにはいかないんで困ってるんですよ。
一方で、財政力のある自治体は、学校給食の無償化っていいますかこれ全体を3割ぐらいです。これ学校経営にとっても厳しい状況になってるんです。子供たちの給食、栄養大事じゃないですか。特に米が高過ぎて困ってるような状況が出てきているということ。それからもう一つ、病院なんですよね。病院の食事っていうのは、健康保険法で決まってますからね値段が30年で、ほとんど上がってきてないんですね、上がってきてない中で、病院食の提供ってのは物すごくこれ大変で、栄養も考えなければいけない。入院してる間に元気になってほしいという思いを持ちながらも、これも相当に苦労してるという状況が今生まれています。こういうね、給食の現場、学校給食の現場とか、あるいは病院食、こういうところに無償提供するような可能性、ないんでしょうか。御検討いただけないでしょうか。提案させていきます。
小泉農水大臣:
思いとしては受け止めさせていただきたいと思います。一方でこども食堂等に対して無償交付、これを行っているのは、目的が食育ということがあり、対価を得て運営をされている施設の経常的な運営経費の支援に充てるのは難しいというふうに理解をしています。
一方で、政府の備蓄米の売渡しに当たっては、集荷業者、卸売業者、小売業者の方々にも、病院や学校給食等への備蓄米の円滑な供給に配慮いただくようにお願いをしてきたところであります。法律の中にもですね、この主要食糧の交付は、主要食糧を試験研究または教育の用に供しようとする場合に行うことができるという、こういった書きぶりでありますので、今の代表の提案を受け止めつつ、法律にのっとって、できる限り現場に、病院など、様々なところに配慮が行くように、通知などはしてるんですけども、しっかりと目配りをしていきたいと思います。
野田代表:
かつて、お父様の時代の小泉政権下で、社会保障費を自然増2200億円削るということをやりました。あのときも病院大変だったんですけど、今回ね、インフレ下の病院って物すごい今大変なんですよ。病院経営、特に公立病院の赤字など深刻です。その中で、病院食でも物すごい苦労してるという状況がありますので、さっきの学校給食の問題含めて、今、法の解釈の話されましたけども、随契についても、果敢に解釈に挑んだわけなので、ぜひこれ前向きに検討していただきますようにお願いを申し上げたいというふうに思います。
今後のことについて、触れていきたいと思うんです。先ほどの生産者の配慮について私お願いしましたけれども、かつて我々が、農家の戸別所得補償制度を導入したとき、これは旧民主党政権の時代ですが、大臣の評価とても厳しい評価だったというふうに私は思っています。でもね、大臣のお考えはこれから多分、米はもっとつくりたい人がもっとつくればいいと、どんどんつくったほうがいいというお立場ではないかと思うんですね基本的には。いわゆる生産の目安などありますけども、そういうものを乗り越えてつくりたい人がもっとつくっていいんじゃないかというお立場ではないかと私は思いますけど、そうすると、国内需要を超えて生産をすると、米価が生産コストを割り込む懸念が出てまいります。そういうときに、米のトリガーというのを発動して、主要主食用米を生産する販売農業者に交付金を交付する。食用米の直接支払い制度、これを導入したらどうかという提案を我々しています。これについての、大臣の御見解をお伺いをしたいというふうに思い
小泉農水大臣:
これは立憲民主党さんから、様々提案をいただいてる一つの主食用米直接支払い、これが米のトリガーと、こういうふうに称されてるという、承知をしています。私が承知しているところだと、これを予備費約100億円ということで、御活用されようというアイデアだと思います。
ただ一方で、今後考えたときに方向性として私は意欲ある方にお米をつくっていただきたい。それは代表がおっしゃったとおりの思いを持ってます。ただ、マーケットがない中で、つくるだけつくって、つくれって言ったんだから、国は買上げなきゃ駄目だとかそれは全く違うと思います。ですので、しっかりと意欲のある方につくっていただける環境等、そしてまた、余ったら海外に売ればいいって言う方よくいるんですけども、海外のマーケットでマーケットメイクをしてない中で、それをやって、なかなかマーケットメイクは出来ませんので、しっかりとこの海外の販路開拓ということは、きめ細かく、やはり体制整備や、様々な流通や商社や、様々な方との協力関係を構築しなければ、そんなに安易に余ったから外へ出すってことは、難しいと思います。
ですので、しっかりと今後の方向性の中では、つくるなっていうことではなくて、しっかりと需給に応じた生産、需要に応じた生産というものが、かなうような形で方向性を考えつつ、まず目の前で、このお米の異常な高騰を抑えて、中長期のことも、政府挙げて検討していければと思っております。
野田代表:
当面、消費者を意識した農政で進めていくということについては一定程度私は理解をすると申し上げます。米離れって心配です確かに。この間の党首討論のときに、総理に、1人の人間が1年間に食べる米が35キロって私が言ったら、すごい反響があったね。50キロじゃないかっていうんですよ、多くの人から。2022年の政府の調査だと50キロです。これ一般的広がってますけど、今年の3月にある独立行政法人が、調べたら35キロになってたんで、ちょっと衝撃を受けたんで、35キロって言ったら世の中に知れ渡ってなかったんでみんな驚いちゃったみたいですけども、それぐらいにもしかすると、調べてる期間が違うんでね、何と整合性ないかもしれませんが、米離れ進んでるんじゃないかと私も意識があるんで、そちらに対する対応は大事だと思います。
一方で、一方でですよ、やっぱり生産者がね、こんなんじゃやっていけないと思って農業から離れてしまうことの危機感、農業基盤っていうのはやっぱり農地と農業者だと思いますんで、農業者が減っていく、米をつくる人が減っていくことに対する危機感も強く持たなければいけないという意味で、さっきのトリガーっていうのは、有効な方法だと思いますので、ぜひ前向きに検討していただきますようにお願いを申し上げたいと思います。