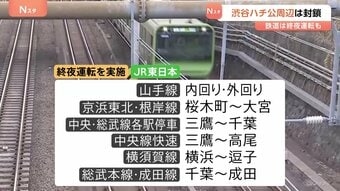国会ではコメ問題で論戦です。備蓄米をめぐり、小泉農水大臣に野党側から「バナナのたたき売りではないか」と追及する声が出ています。小泉農水大臣と立憲・野田代表のやりとり全文です。
コメの価格高騰の原因は?
野田代表:
具体的な問題に入る前にですね、基本的な認識をお尋ねをしたいと思うんですけども、今日は、米の高騰、米価の高騰について絞って、質問していきたいと思うんですけれども、米価の高騰の原因なんですけども、これは昨年秋の猛暑のまさに不作の問題と、あるいは訪日客が急増したという消費増などの、まさに米不足が原因だったのか、それとも流通の問題ですね。目詰まりの問題。どちらかというと前大臣は、こちらが真犯人じゃないかと思ってたように思うんですけども、大臣はどうお考えなのか。というのは、やはり、問題の本質をよーくつぶさに検討して理解しておかないと、問題解決は出来ないと思うんです。正しい処方箋を書くには正しい診断が必要だと思うんです。まず基本認識からお伺いしたいと思います。

小泉農水大臣:
今、野田代表のほうからは、高騰の理由は何なのかと。前大臣の思いというのは、流通の目詰まりだったんではないか、私はどう思ってるのかということでありますけども、今代表がおっしゃった中で、私も複数いろんなところから声を聞きます。インバウンドの消費が予想よりも多く、米の消費につながって、結果として不足感が出てるんじゃないかとか。そういったこともありますが、ただですね、この6年産米については、生産量は前年より増えてるんですよね。減っていて今不足なのではなくて、18万トン増加する中で、減っているのはどこかというと、全農さんを初めとする集荷業者への生産者の出荷量が減ってるんです。集荷量が31万トン減少している。なので、恐らく一般の方からすると、こんなに足りないから米の生産量が減っているというふうに思ってる方はいらっしゃるかもしれませんが、実はそれは増えているんです。ただ、集荷量が減っている。
ですので、こういったところがどうなのかというのが、流通全体を見て検証っていうのは、私は代表がおっしゃるとおり今後必要だと思います。減ってるところ、どこが増えてるかっていうと、この集荷業者以外のところが増えてるんですよね。ここが前年より44万トン、増えているということであります。この結果、例年とは異なる調達ルートとして、業者間の取引市場から、スポット的に高い価格で仕入れることが必要となったと。ですので、これは私は生産者の方と、この前日曜日に埼玉県に行って米農家さんと話をしたときに、これは全国植樹祭の後にお話をしたんですが、今、スポットで5万っていう数字なども出たりしている中で、何も手を打たないと、もしかしたら、それは6万とか、さらに上がりかねないような状況なので、ここは、備蓄米の放出っていうのも、理解をできるっていう声を生産者からもいただきました。
こういったスポットで高い価格が入っていることも、一つは、今現状としてはあります。また、米の不足感が継続する中で、集荷業者から生産者に支払われる概算金が前年と比べて高い中で、集荷と卸の間の相対取引価格、これも秋以降継続して上昇しているともに、端境期まで在庫を持たせなきゃいけないっていうことをやはり卸の皆さんも考えますから、あまり大量に出さずに、少しじわじわと出さなきゃいけないっていうことも含めた、やはり不足感というものが、棚の現状だったり、消費者の皆さんの感覚としても、私は出ているのが現状なのではないかなと捉えています。