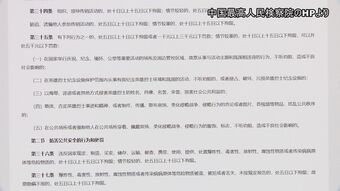「バナナのたたき売りじゃない」コメの適正価格をどう考えるか
野田代表:
財政法のお話出ましたけれども、従来はこれ法的な解釈が厳しいなと言われてたのが財政法の29条の3の4項、契約の性質または目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することが出来ない場合、及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところに随意契約によるものとするということなので、緊急であるとか、ということを意識したんだと思うんですけども、昨日の我々の部会の中では、この政令に定めるところによるってのはどこなんだと。聞いても、回答がなかったと。今日まで来てないということだったんですね。
そこはしっかりと明確に答えられるようにしておかないと、私今日はちょっと法令上の問題ぐりぐりは止めようとは思ってません。ここは今日はスルーしますけれども、しっかりと根拠を説明した上でいかないと、法治国家ですので、しっかりとその対応をお願いをしたいと思います。
ですが、これは先ほど鈴木貴子委員の質問にも重なるんですけれども、この米の適正価格について、総理が、5月21日の党首討論のときに驚くべきことに、金額を明示して、3000円台とおっしゃったんですね。いや、驚いたんですけども、これも驚きましたけれども、たちまち、農水大臣就任されてから、2000円程度と、もう3000円でも驚きましたけども、2000円と数字を明確にされたということなんです。バナナのたたき売りじゃないんで、気合は分かるんですけども、それが適正価格かどうかということなんですね。適正価格というのは、消費者にとっては安いほどいい、これ間違いないです。一方で先ほど出てきているように、生産者にとっても、適正価格は何なのかということを、バランスよく考えていかなければいけないじゃないか、農政というそういうもんじゃないかと思いますけども、いかがでございますか。
小泉農水大臣:
これよく今でも混同されて、報じられることもあるので、ちょっと丁寧に説明させていただくと、石破総理が3000円台と言ってるのは、全国の平均の、今4200円と出ているものを、3000円台に持っていきたい。こういった意思を述べています。
私が2000円と言ってるのは、今の4200円を落ちつかせていくためには、2000円の備蓄米を放出しなければいけない。そして今回、この2000円が適正かということで御質問をいただきましたけども、生産者の方にとって、今の様々な物価や資材の高騰や人件費の高騰などを踏まえたら、この2000円が生産者の方にとっての適正ではないと思います。
しかし今回、我々備蓄米を、古い備蓄米を出しますので、この古い備蓄米をおろしていく価格としては私は適正だと思います。ですので今回は、高過ぎているマーケットを、2000円の備蓄米、そしてこれから新たな随契では1800円とか出てきますけども、こういったものを入れることによって、確実に安定した方向に、下がっていくということをもって、生産者の皆さんに、消費者の米離れを防ぐんだと、こういったことを御理解をいただくということを丁寧に進めていきたいと思います。
野田代表:
数字をお話しするときはやはり丁寧な御説明を、総理も足りなかったと思いますよ。大臣も今のお話では、少し理解できるようになりましたけども、ぜひ丁寧な説明を努めていただきたいと思うんです。その上でですね、当面は米の値段を下げることに主眼を置いて、消費者の観点で進めるという姿勢を強めていらっしゃるということだと思うんですね。
ただ私はバランスってのがあって、さっき納得価格ってお話をされてましたけど、生産者すごい今不安でね、3000円台でもきついなと。2000円台なったら、とてももたないなと思ってる人たちがたくさんいらっしゃるんです。その人たちのことも配慮するような政策をこれから随時出していかないと、バランスを欠くと思ってるんですね。今はね、例えば消費者の視点でという右足を出すと。でもいずれはね、やはり生産者のことを考えてますよと言う左足を出す。やっぱり、右足ばっかりいっちゃったらバランス悪い農政になりますよね。右足左足と進めながら前進するものだと思いますので、その辺のバランス感覚というものもあるぞということを、ぜひこれからはお示しをいただきたいというふうに思うところであります。
備蓄というのはこれは玄米じゃないですか。この玄米は、私は精米や袋詰めというところがネックになっていて、これまでの入札によるいわゆる売渡しにおいては、なかなか店頭に出てこなかったというのは、例えばJA全農などに売渡したけれども、この袋詰めとかね、いわゆる精米の問題がやっぱりネックになってる部分があったんじゃないかと思うんです。精米や袋詰めをどう克服していくということをしっかり考えていかないと、消費者に提供されるには時間がかかってしまう可能性があると思いますけれども、それについての大臣の御見解をお伺いしたいと思います。