教育現場にも「インクルーシブ」
なぜ、いまインクルーシブが広がっているのか?大きな理由の一つが2015年に国連で採択された、持続可能な開発目標「SDGs」です。
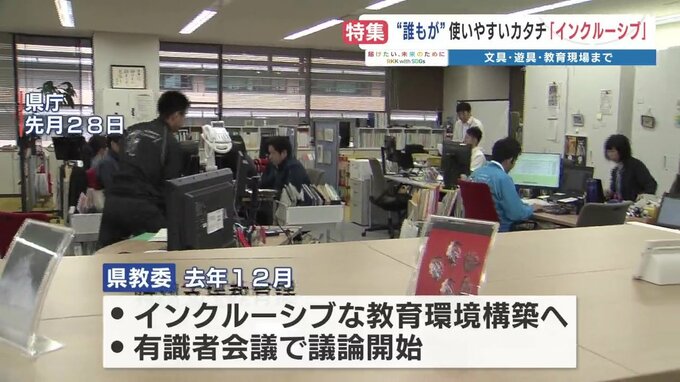
インクルーシブ社会の実現は、「誰一人取り残さない」という「SDGs」の推進にもつながっています。熊本県教育委員会もインクルーシブな教育環境をつくるために去年12月、有識者会議での議論を始めました。
熊本県教育委員会特別支援教育課 西坂紀彦課長「目指すところは共生社会。障害
がある人も無い人も、お互いを尊重し理解しながら、ともに暮らせる社会を目指す」
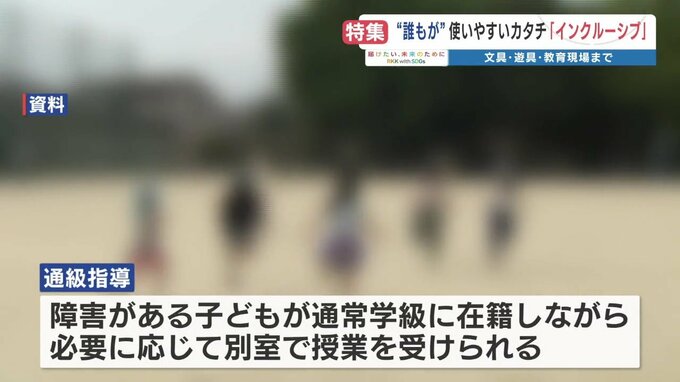
近年、熊本県教委が力を入れているのが「通級(つうきゅう)指導」です。障害がある子どもが通常学級に在籍しながら、必要に応じて別室で授業などを受けられる仕組みです。
熊本県教育委員会特別支援教育課 西坂紀彦課長「障害がある児童生徒が通級指導で、通常の学級でしっかり学ぶことができればインクルーシブかなと思う」

熊本県内で特別支援学校に通う児童生徒は昨年度が2394人と、10年前の1.5倍に増えています。日本語指導が必要な外国籍の児童生徒も同じくて2.5倍に増えていて「共生」の重要性は高まる一方です。
熊本県ではTSMCの進出でさらに外国人の増加が予想されています。外国人、障害の有無、年齢、性別などに関係のない共生社会の実現に向け、いま多くの現場で模索が続いています。














