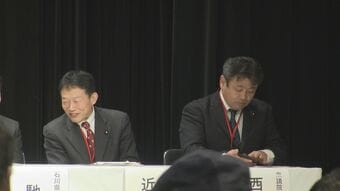能登半島地震で大きな被害を受けた輪島市門前地区にある国の重要文化財・総持寺祖院の寺の運営などを統括する新たな監院(かんいん)が着任し、復興に向けた取り組みを進めることになりました。
700年以上の歴史を持つ総持寺祖院は、これまで大勢の修行僧を受け入れてきましたが、能登半島地震により境内にある多くの建物が被害を受け、地震以降は1年以上、数人の僧侶だけで交代しながら寺を守ってきました。

こうした中、寺の運営などを統括するため新たに勝田浩之監院が着任しました。
金沢市出身で68歳の勝田監院は、横浜の大本山総持寺で10年間副監院を務め、今回祖院の再建を託されました。

修行に訪れた僧侶が寺に入る時に必ず叩く木版と呼ばれる木の板を3回叩いた後、お釈迦様生誕の日に合わせた着任式に臨みました。
自身もかつて、この場所で修行を積み重ね思い入れの深い総持寺祖院の復興を心に誓います。
勝田浩之監院「まずは、この痛んだ建物を復興するというのがやはり一つの目的でもあります。それとまたここはやっぱり修行道場でございますので、修行僧がやっぱり来なければやっぱり活気がないということもあります。ゆくゆくは修行僧が、一人でも二人でも修行ができる、そういう道場に、また元の総持寺祖院にやっぱり戻したいという気持ちがありますね」

髙島弘成副監院「(新監院を迎えて)今年に入ってから、復興に向けてようやく一歩を進みだしたところで、地元出身の方でここにもご縁の深い方ではありますので、やはり下の私たちにとっても心強い存在になって頂けるという風に思っております」
16の建物が国の重要文化財に登録される総持寺祖院の修復には9年以上、かかる費用は38億円と見込まれる中、住民ととともに復興へと歩む気持ちを持ち続けます。