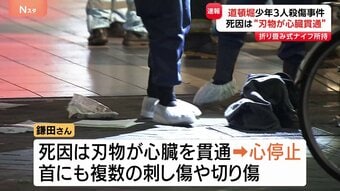民放の公式テレビ配信サービスとして、いまや誰もが知る存在となった「TVer」。今年秋に10周年を迎えるにあたって同社の常務取締役である蜷川新治郎氏にインタビューし、これまでの苦労や次の目標などについて聞いた。聞き手は、メディアコンサルタントの境治氏。
テレビ東京出身の蜷川新治郎常務
民放テレビ局の見逃し配信サービス「TVer」は2015年10月にサービスを開始し、今年10周年を迎える。ここ数年の成長は目覚ましく、発表のたびに月間視聴数が億単位で示される。地上波での放送収入がはっきり頭打ちになっているいま、テレビビジネスの成長性を託されていると言っていい。キー局各局の決算資料でも「配信広告収入」の数字が明示され、前年比で30〜40%台の驚異的な伸びとなっている。
TVerはもともと、キー局のネット展開をサポートするために設立された株式会社プレゼントキャストが受託する形で始まった。2020年にはキー局が満を持して同社に増資し、名前も株式会社TVerとなった。その際、各キー局で担当していた人びとがTVerの取締役になっている。
テレビ東京からはスタート時からTVerに携わってきた蜷川新治郎氏が赴任し、現在は常務取締役だ。筆者は蜷川氏がテレビ東京在籍中から配信事業について様々に話を聞いてきた。2023年にもInter BEEで筆者MCによるパネルディスカッションにお招きし、議論してもらっている。
今回は、10周年についての取材を受けると蜷川氏がアナウンスしていたので、真っ先に申し出た。10周年を讃えつつ、言いにくいことにも突っ込むとあらかじめお伝えしたが、快く取材を引き受けてくれた。
成功したのは、“当たり前”に追いついただけ
境 TVerは今年で10周年を迎えます。現在の規模はどのくらいになっているのでしょうか?
蜷川 現在は月間ユニークブラウザ数(MUB)4000万人、月間再生数5億回弱(2024年12月)という規模にまで成長しています。

境 この10年間での成功の理由はどこにあると思いますか?
蜷川 すごくシンプルに言うと、“当たり前のこと”に追いついたということです。2014年頃から、インターネット上での動画コンテンツの流通が放送を凌駕するんじゃないかという危機感はありました。ユーザーから見れば、スマートデバイスやパソコンでテレビコンテンツが見られないのはナンセンスだったのです。でも放送業界としては「2兆円の売り上げを崩していいのか」という懸念がありました。
境 配信サービスへの参入は必然だったということですね。
蜷川 そうですね。YouTubeやNetflix、Amazon Prime Videoなどの台頭により、我々がやらないと奪われていくものだったのです。コンテンツの強さもどんどん弱くなりかねない。見てくださる方が減っていくわけですから。
境 サービス開始当初は業界内での抵抗もありましたよね?
蜷川 はい、「無料で見せるとカニバる(注)じゃないか!」という声も多かったです。テレビ東京時代、ある番組の配信が全局1位になった際、役員会で報告したところ、「リアルタイムの視聴率がよくなかった原因」となり、のちにこの番組の配信が止められたこともありました。
当時はそういう時代でしたね。「これからこうなるんだ」と取り組む人と、「こんなことやったら損する」と考える人がいて、相当、局、立場、人によって差がありました。
(注)カニバる…「共食い」を意味する「カニバリゼーション」を語源とするマーケティング用語。