■「在庫=悪」が常識の時代から“激変”
――長引くコロナ禍の影響で、給湯器の品不足が深刻化していた。その背景には何があったのか。
リンナイ 内藤弘康社長:
我々の会社では、最初に九州のマイコン(半導体部品)を供給してもらっている会社で工場の火事がありました。それで大騒ぎして、茨城の別の会社のマイコンにすべく体制を整えていたら、今度はそちらの会社でまた火事があって。さらに、それまでコロナではうまく対応していたベトナムで、コロナが猛威を振るうようになってロックダウンして、今度はノイズフィルターという部品が入らなくなって、これでまた大騒ぎになったのです。
そうこうしているうちに、電気回路をつなぐハーネス(回線)が足りなくなったと。あらゆるものにわたって部品が不足したり、材料自体も不足したり、それから物流も船に乗らないだとか、船が足りないだとか。さらにトラックの運転手さんが足りない。だからもう物流網もズタズタですね。
――ついこの間までグローバル化時代だと言って、世界中のどこからでも最適なものが買えるという前提で世の中が回っていたが、突然変わってしまった。
リンナイ 内藤弘康社長:
変わりましたね。いままで効率よく、頼んだものがきちっと入ることを前提に生産計画を全部組んでいましたから、生産形態がいままでとは全く違ってくるというか、判断基準がいままでと全く違ってくるというのが頭の痛い問題で。
いままでこの地域(東海地方)は、まさにトヨタさんをお手本にトヨタ生産方式で鍛えられた企業が多く、それは確かに素晴らしいものなのですが、いまはそれは怖くてできないですね。やはり中間在庫を多めに持つとか、製品在庫も多めにするというふうになってきました。
――製品のコストも上がってきているのか。コスト増の価格転嫁は?
リンナイ 内藤弘康社長:
すごく上がっています。資材費はこの1、2年で100億を超えて上がっています。今年の4月からお願いして価格改定はしていますが、その後の状況を見てもなかなか厳しいですね。いままでやっていた企業努力の範囲を超えているなということは感じています。
内藤社長は「サプライチェーンの問題はこれまでと全く風景が違う。いつまで続くかというよりも、もう変わらないのではないか」と語った。日本の製造業を取り巻く環境が変わったということなのか。ニッセイ基礎研究所の矢嶋康次氏に聞いた。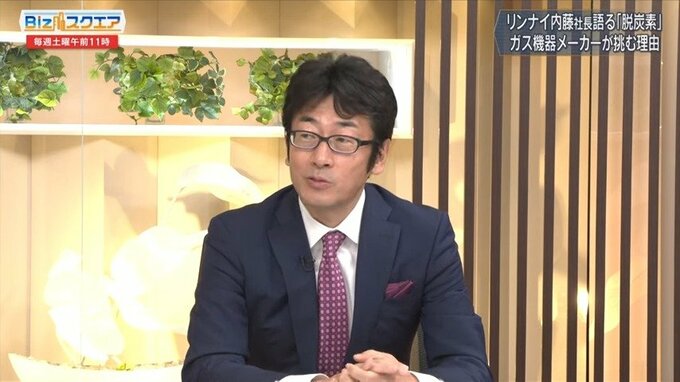 ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:
ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:
今年に入って経営者と話していて変わったなと思うのは、「在庫」という言葉です。昔は在庫は悪、持ってはいけないという話でした。最近聞くのは、在庫を持っていて利益が出る、つまり値段が上がるということです。そういう構造になってくると、経営の判断として在庫はある程度持たなければならない。
CO2の対応、環境の対応をしなければならないと考えると、コスト増の要因ばかりです。企業は利益を出さなければならないので、コストが増えて利益を出すということは、やはり生産性をいままで以上に上げなければならない。ここが、いままでの延長線上の生産性のあり方では対応できないという経営者の方が多いです。
――コストが上がるので価格転嫁、インフレの時代にならざるを得ないということか。
ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:
そういう意味では川下に向けてどんどんインフレの構造がこれから出てくると思います。
――ミクロで変わっているので、マクロの経済構造もそれに合わせたものにどう変えていくかということだが。
ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:
社会の構造を変えないとダメだと思います。
(BS-TBS『Bizスクエア』 10月15日放送より)














