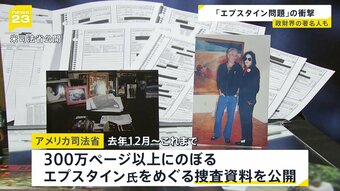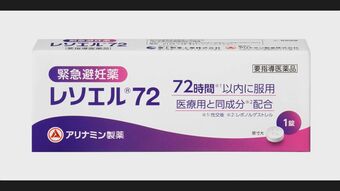選挙報道において、テレビなど既存メディアの存在意義が問われる事例が相次いだ。SNS時代のテレビに求められる選挙報道とは?シリーズ第4回の今回は、法政大学教授でジャーナリストの藤代裕之氏が国内ニュースの「生態系」を踏まえて考える。
2024年は東京都知事選挙、兵庫県知事選挙と、相次ぐ首長選挙で既存メディアの存在意義と信頼性が問われた。世論調査を伝える情勢報道が外れ、SNSの影響力に注目が集まるのは2016年アメリカ大統領選挙を想起させ、「SNS vs 既存メディア」といった構図で捉える報道も相次いだが、個人的には違和感がある。
SNSが影響力を増しているのも、既存メディアの影響力が低下しているのも事実ではあるが、テレビ局には果たすべき役割があるのではないか。
国内のニュース生態系を踏まえる
「SNS vs 既存メディア」という議論から抜け落ちているのは、インターネットにおけるニュースの状況だ。日本ではニュースはSNS・ソーシャルメディアよりも、ポータルサイト経由で触れられていることが多い。
新聞通信調査会の調査によると、インターネットニュースを見る時にアクセスするのは、ポータルサイト(Yahoo!やGoogleなど)が81.8%と突出して多い。SNS(LINE、X、Facebookなど)は34.3%、新聞社・通信社・テレビ放送局の公式サイトは13.8%となっている。18-19歳、20代では、SNSがポータルサイトより若干多い。
ロイタージャーナリズム研究所の「Digital News Report 2024」の調査によると、日本におけるニュースの情報源はオンラインではYahoo!ニュースが突出している。また、ポータルサイトのようなアグリゲーター(各種のコンテンツを集約・整理して、提供する事業者)を情報源にするのは日本が36%に対し、世界平均は8%、ソーシャルメディアは日本が8%、世界平均は29%となっている(注1)。
これらを踏まえれば、選挙に関するメディアの影響を考えるにあたりSNSだけでなく、Yahoo!ニュースなどのポータルサイトの状況は無視できないということになる。
ポータルサイトには、テレビや新聞だけでなく、週刊誌、ネットメディア、個人まで幅広い媒体が記事を配信している。Yahoo!ニュースによると、パートナーであるメディア企業460社、730媒体から、毎日約7,500本もの記事が配信されている(注2)。
多様な媒体だけでなく、週刊誌のスクープ記事から、取材が不十分な「こたつ」記事まで、同列に読者に届けられていることも特徴だ。記事には専門家やユーザーのコメントが付与されたり、SNSに共有されて議論を巻き起こすこともある。
このような複雑なインターネットのニュースの生態系を踏まえ議論する必要があり、「SNS vs既存メディア」と単純化することは問題を見誤りかねない。