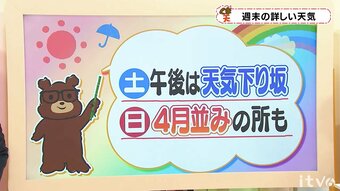「家事を手伝う」と言われて、なぜか心がモヤっとする――。
「簡単でいいよ」の一言が、かえって相手を追い詰めてしまう――。
そんな家事をめぐる夫婦間のすれ違いは、多くの家庭が抱える悩みではないでしょうか。
この問題に対し、愛媛県の少子化対策・男女参画課が発行した冊子「家事シェアスタイルブック」が、具体的なコミュニケーション術で解決の道筋を示すとして、注目を集めています。
冊子では、家事のやり方が違うのは、お互いの母親という別々の“お手本”がいるため当たり前だと指摘し、一方的な「分担」ではなく、対話を通じた「シェア」への移行を提案しています。
ここからは、冊子で紹介されている具体的な場面を見ていきましょう。
場面1:休日のお昼ごはん、何が食べたいか聞かれたら…
【地雷ワード】「簡単でいい」
冊子によれば、家事が「簡単」かどうかを決めるのは作業をする本人であり、作らない側が決めつけるのは相手の労力への無理解と受け取られます。また、「●●でいい」という言い方自体も、作る側には「簡単なもので妥協した」というニュアンスで伝わり、気持ちを逆なでしかねません。
【神ワード】「●●が食べたいから、(自分が)●●するね」
この言葉は、単に希望を伝えるだけでなく、「自分が動く」という主体的な姿勢を示すことで、相手の負担を軽くする思いやりが伝わります。受け身の立場から、共に食卓を作る当事者へと変わるこの一言が、円満な家事シェアの第一歩となります。