「集約的な町作り」の先にあるのは…

(財政制度等審議会 増田寛也 会長代理)
「能登半島地震からの復旧復興にあたっては、地域の意向を踏まえつつ集約的な町作りやインフラ整備が必要」
去年4月、財務省の諮問機関は復興に「集約化」を提言。


地方の切り捨てになるのではないか…、議論を呼んだ提言の背景には、東日本大震災がありました。
災害に強い街を目指し、国は6500億円以上を投じて岩手・宮城・福島の3県で
地盤のかさ上げなど1009ヘクタールを整備しましたが、活用率は76パーセントに留まっています。

市の中心部を10メートル以上、かさ上げした岩手県陸前高田市では…。
(鶴亀鮨 阿部和明さん)
「この通りは、今(この時間)からやっているのは俺くらい」
整備された市の中心部で寿司店を構える阿部和明さんには「こんなはずではなかった」との思いも…。

(鶴亀鮨 阿部和明さん)
「時間かかり過ぎたので、みんないなくなった。いい町つくったって話できればいいんだけど、あんまり立派な町ではない」
かさ上げ工事は8年におよび、住民は高台や市外へと移っていきました。人口は4割減り空き地も目立ちます。復興の議論に持ち出された「コスト」と「時間」。
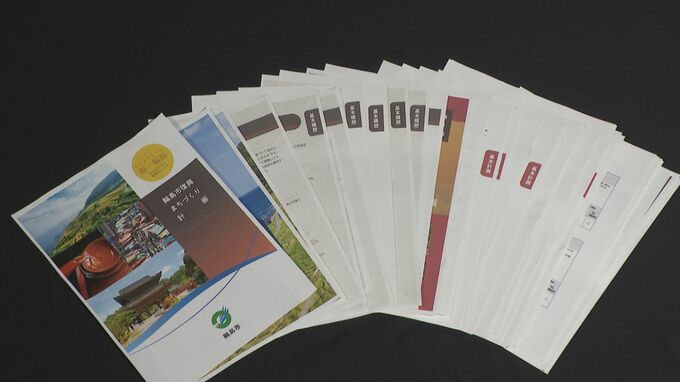
能登の地震で大きな被害を受けた輪島市は復興計画に住民の移転を前提にした「生活拠点の集約化」を打ち出しています。
しかし川岸さんの住んでいた渋田町はその拠点にはならず、復興の対象から外れる可能性が強まっています。

(輪島市企画振興部 山本利治 部長)
「復旧はどんどんしていきたいが、果たして本当に元に戻せるかという場所も正直ある」














