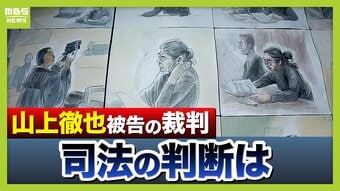放送法を持ち出すのは議論からの逃亡
兵庫県知事選挙の後、オールドメディアの終焉やSNS選挙の萌芽といったテーマで、多くの論評がみられるようになりました(拙稿もその一つではありますが)。それらのなかで見受けられるのが、放送法の規定によりテレビの選挙報道は変わることはできないという、放送法の規定を盾に取った論説です。私は、これらの論説は、議論からの逃亡でしかなく、意味をなさないと考えています。
放送法では、確かに公平性などについて配慮するよう求める条項があります。具体的には、第4条で、「放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。」と定め、「一 公安及び善良な風俗を害しないこと。」「二 政治的に公平であること。」「三 報道は事実をまげないですること。」「四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」とあります。
ただ、法律で定められているのはあくまで上記の条文の通りです。従って、例えば選挙報道における「届出順での報道」や「尺(時間)の平等性」や、「どのような候補者であっても出馬会見を取り上げる」といった運用は、放送法第4条の趣旨を踏まえた業界のルールであり、いずれもそのルール自体が法律ではないため、ルールから逸脱することが違反にはあたりません。
長い年月を経て放送業界がつくった選挙報道の自主規制やルールが、今となってはクロスメディア化された社会に適応できるコンテンツ力をつくる阻害要因となっているのです。