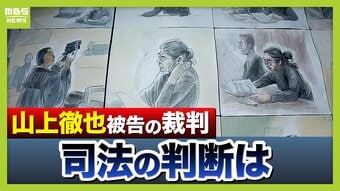クロスメディアでコンテンツの垣根がなくなる
そもそも、テレビやSNSといった「メディアプラットフォーム」の垣根も、近い将来、意識されなくなると筆者は考えています。先の兵庫県知事選挙のあと、有権者インタビューを行うなかで、次のような出来事がありました。
とある高齢の有権者は、選挙における投票行動の際に参考としたメディアに「テレビ」と回答しました。「テレビ」でどのような情報に接し、具体的にどういった投票行動をしたのかを尋ねると、「テレビで兵庫県知事の特集をやっていた。斎藤知事は悪くない人だと解説していた」と言うのです。
それは選挙期間中のことか、と聞くと、「選挙期間中で、候補者の紹介をするテレビ番組だった」と話します。私は違和感を持ってよく聞いていくと、この有権者が自宅で見ていたのは「(インターネットに接続された)テレビで(YouTubeにアップロードされた、放送局のチャンネルの)候補者の紹介をするテレビ番組だった。(動画視聴後、おそらくはリコメンドなどで、放送局のチャンネルではない、別の動画がそのまま連続して再生され、その動画で)斎藤知事は悪くない人だと解説をしていた」ということだったのです。
あくまで、自宅にある「テレビ」で見ていたので、「テレビ」と答えていますが、言うまでもなく、この有権者が接触していた媒体は「YouTube」であり、広義の「SNS」だったのです。
選挙報道番組も、Webコンテンツとしてインターネットにアップされれば、SNSで拡散されるネタの一つになります。クロスメディアが進むなかで、テレビ局の選挙報道自体がクロスメディア化された社会に適応できるコンテンツ力を持ち続けられるかどうかが、テレビ局の選挙報道そのものの今後を左右すると考えます。
先ほど紹介した有権者は、おそらく「テレビ」という箱で映像を見ていたという認識ではあるものの、どこまでが「テレビ的番組」で、どこまでが「YouTube的番組」なのか、その明確な境界線を意識しなかったから「テレビ」と回答したのでしょう。
拙稿をお読みいただいているような方であれば、さすがにその境界線は見ていて気付くとは思うのですが、今後ますますクロスメディアが進めば、テレビとYouTubeの境界線は薄くなるでしょう。
そもそもYouTubeはテレビ制作に対するカウンターやアンチテーゼの側面として発展してきた経緯があります。さらにオンライン動画サービスの多くはフラットなゆえに純粋なイデオロギー対決の場になっていて、テレビは追いつけてない現状があります。
従って、「テレビ」と「YouTube」の垣根がなくなろうとしているタイミングで、まさに「むき出しのイデオロギー対決」となっているYouTubeが流行れば、見よう見まねで同じようなコンテンツをテレビ局がやってみようという挑戦がはじまり、(テレビ局が、YouTubeで流行った動画を収集してタレントとともに鑑賞するバラエティ番組のように)結果的に選挙の映像コンテンツそのものも似てくるようになるかもしれません。