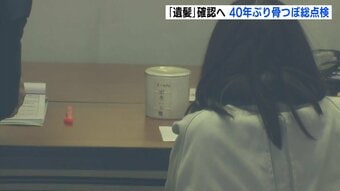阪神・淡路大震災から30年が経ちました。この30年で全国で大きな地震が相次いで発生しました。そして南海トラフ地震をはじめ各地で地震が起こるリスクが指摘されています。
1年前に起きた能登半島地震では、死者は災害関連死を含めると500人以上。被災地は、映像だけでは伝わりにくい過酷な現場でした。地震発生直後に被災地を取材したRCC記者が、特に大変だったと感じたのが「トイレ」です。今回は災害時の「トイレ事情」について考えます。
被災地を取材したRCC末川徹 気象予報士
「当時は、10センチほどの雪が積もっていました。シャワーや風呂にも入れませんでしたが、個人的に苦労したのは『水洗トイレが使えなかった』ことです」

2024年1月、震度6強の揺れを観測した石川県・珠洲市です。避難生活が長期化するなか「いま困っていること」を尋ねました。
中学生
「トイレの水が流れない」
珠洲市の町内会長
「トイレが一番大変。1人ずつゴミ袋を持ってもらい、まとめてゴミで出す」
珠洲市では、津波や液状化により広い範囲で断水。通常のトイレが使えませんでした。袋に用を足す「災害用トイレ」に、被災者も困惑していました。