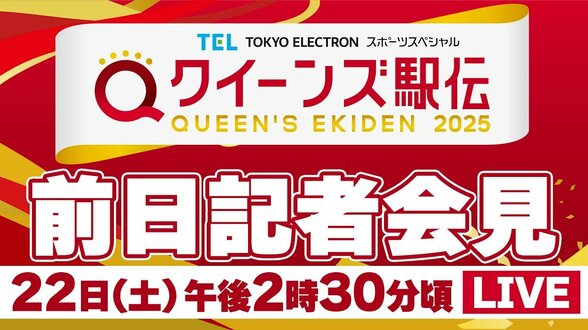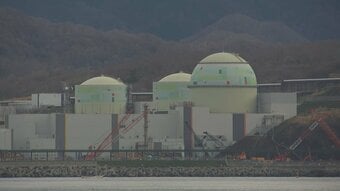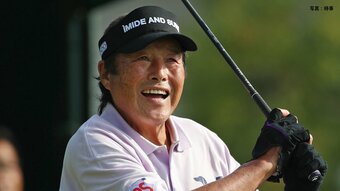ボストンとは違った練習パターンで
ニューヨークシティ・マラソンに向けての練習は、ボストン前の内容を踏襲したり、これまで培った経験を総動員したりして行っている。その一方で、成功体験に縛られず柔軟な発想ができるのが森井勇磨という選手だ。スピードがない欠点を踏まえたり、拠点の原谷の起伏を活用したりするのは変わらないが、ハード的にもソフト的にも、新たな取り組みを導入した。
1つは7月に四条烏丸にある低酸素室の施設と契約し、疑似高地トレーニングを行い始めた。その施設のトレッドミルが自走式であることで、森井のやりたい練習内容ができた。
「1000mの準高地や1700mの高地でトレーニングをしたことはありましたが、そこまで効果を実感できませんでした。四条烏丸の低酸素室は標高3000mの環境も作ることができ、心肺機能への負荷をかけることが30分のジョグでもできるんです。心肺機能だけでなく胸筋や手首近辺にも、適切な負荷がかけられます。自走式トレッドミルは、電動であらかじめペースを設定する従来のものと違い、自分で走ってペースを調整できます。追い込み方を柔軟に変えられて傾斜もついているので、トレッドミルなのに変化走、ファルトレーク、インターバルと、トレーニングの種類をいくつもイメージして走ることができます」
レースの活用法も変えた。ボストン前は連戦して合わせたが、今回は出場レース数を抑えている。8月25日の北海道マラソンは6~7月に中足骨の疲労骨折をした影響で2時間21分18秒(12位)だったが、その後は9月21日の5000m(14分29秒73)と28日の10000m(29分34秒97)まで、トレーニングに専念した。
9月の走行距離は879kmで、ボストン前の同時期は760kmだった。「暑さがあった分、単純な比較はできない」としながらも次のような違いを感じている。
「マラソンは集中してトレーニングをする期間も必要だと感じていました。5000mと10000mに出た週も、京都は35℃前後の日も多かったのですが、その暑さの中でも走り込みました。ポイント練習は少なくした代わりに、120分以上や30km前後のジョグが、ボストン前の9回から12回に増えました」
10月は13日に舞鶴赤レンガハーフ(1時間05分55秒・優勝)、20日に東京レガシーハーフと走るが、前述のようにボストン前の連戦と比べたらレースで刺激を入れる回数は少ない。
「練習でもポイント練習や刺激(スピード練習)の割合が少なくなっています。ジョグがメインでも脚を作っていれば(“脚を作る”はランナー用語で長い距離を走り切る能力のこと)、試合用の調整なしで14分半、29分半のレベルで走ることができています」
紹介してきたように原谷の起伏や、自走式のトレッドミルを活用すれば、持久的なメニューでもスピードを上げられる。1km2分30秒台なら、無理なく出せるようになっている。
10000mの自己記録は大学4年時に出した29分07秒93で、昨年の日本選手のシーズンリストでは500位前後に相当する。森井本人は「スピードがない」と話すが、実は“スピードも出せる”タイプの選手ではないかと推測できる。東京レガシーハーフマラソンでは、序盤でそのスピードが見られるかもしれないし、レース終盤では、9月の走り込みでいっそう強化されたスタミナが発揮されそうだ。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)