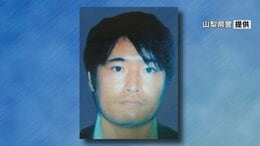壮絶な闘病生活 激痛にパニック障害

両親と2人の姉をもつくらんけさんは、末っ子として家族から溺愛されて育った。しかし、6歳の時にCIDPと診断されたことで、幼くして壮絶な闘病生活が始まることになる。
ステロイド薬の大量投与と免疫療法など、あらゆる治療を尽くした。その度に頭痛や発熱、吐き気などの副反応に襲われた。
全てをなげうって支えてくれる両親に「悲しい顔をさせてはいけない」との思いから、どんなに痛みが伴う治療や検査でも涙を流さずに耐えた。小学生の頃から「全ての感情に蓋をしてきた」という。
6歳から20年以上にわたる治療は、激しい苦痛にも関わらず目立った効果がなく、心を徐々に蝕んでいった。
検査に伴う副反応で鼻の粘膜を削り取る手術をした際は、激痛がトラウマとして残り、パニック障害にまで発展してしまったという。
幼い頃から感情に蓋をして「頑張り屋さん」と認識されていたくらんけさんが、泣きわめく姿を周囲に見せるようになる。彼女がこれ以上の治療を望まないことを伝えると、主治医からは完治の見込みはないと、はっきり告げられた。
「死にたい」娘のエゴ 「生きてほしい」親のエゴ

この頃から、安楽死の選択を考え、家族にも伝えるようになった。CIDPは投薬を続ければすぐに命に関わる病気ではないが、終わりが見えないことが何よりも辛かったという。
家族全員が安楽死に強く反対した。特に両親は「一生懸命育ててきたかけがえのない存在。どうしても死んでほしくない」と懇願した。
だが、くらんけさんにとっては、そんな大切な家族だからこそ、「両親や2人の姉に介護させる一生なんて、絶対に嫌だ」と譲らない。
最終的には両親も「親のために生きてくれとまでは言えない。賛成はできないが、自分たちのエゴで反対もできない」と折れてくれた。
くらんけさんは、海外で安楽死を認めてくれるスイスの団体に申請し、2019年10月に許可が下りた。「これで全てが終わる」と解放感に包まれる一方で、家族への一抹の不安を心の奥底にしまい込んだ。
「私がいなくなった後、この両親はちゃんと生きていけるだろうか」