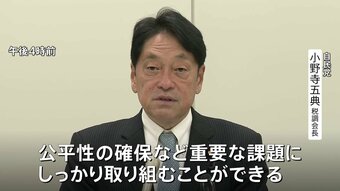故郷を護るために…ゲリラ戦を強いられた 少年たち

80年前、ふるさとを護るために結成された少年部隊がある。
「護郷隊(ごきょうたい)」だ。
激しい地上戦で兵力が不足する沖縄。国は、兵士に代わって10代の少年たちを召集した。その数、約1000人。 与えられた任務は、敵に気づかれず、奇襲攻撃を繰り返すゲリラ戦。本土決戦を遅らせることが最大の目的だった。
沖縄県中部の山岳地帯に、今も護郷隊が活動していた痕跡が残されている。地元の研究者に案内してもらった。
恩納村史編さん係 瀬戸隆博さん
「こちらがいわゆる蛸壺壕、兵が身を隠していた場所ですね」
少年たちが潜んで戦ったとみられる蛸壺壕。この山中では40か所ほど確認されている。
瀬戸隆博さん
「できるだけ敵を1人でも殺して、アメリカ軍を1日でも長くここに引きつける」
「まさに時間稼ぎのために「捨て石」と言っていいのかもしれない、そういう意味では」
存命する元少年兵を訪ねた。

17歳で入隊した宮城清助さん、96歳。
わずか3週間の訓練で実戦に投入された宮城さんは、アメリカ軍の侵攻を食い止めるために橋を壊したり、敵が寝静まったのを見計らって夜襲をかけたりしたという。
元護郷隊員 宮城清助さん(96)
「昼は隠れて行動しないで、夜になると(行動する)。掃討戦の中に入ってしまっているから。生きて帰れるかなと不安はありました」
宮城さんには今も忘れられない記憶がある。
移動中に手榴弾が暴発して死んだ仲間の姿だ。

宮城清助さん(96)
「はらわたをえぐり取られて、アンマ、アンマ(お母さん)と断末魔の」
「15分ぐらいは生きてますよ。ここで死んで」
敵の攻撃から逃れるため、死んだ仲間は置き去りに。それでも可哀想という気持ちは湧かなかったという。
宮城清助さん(96)
「教育のおかげで、軍隊に憧れていく、これがその時の思想です」
「16、7歳で、そういったことに疑いを持つということはないです」