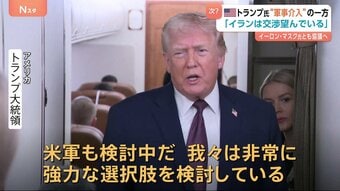「観光」のために「地域」があるわけではない
観光とは、ある意味、「分かち合い」である。地域の恵みや持ち味、そこで育まれ伝えられてきた知恵や技を訪れた人々に分かち合うことが観光なのではないか。美しい自然や貴重な文化遺産を守ってきた人たちがいるからこそ我々は旅を楽しみ、地域の「“光”を観る」ことができる。
人々が訪れた地域に対して敬意を払って観光をする。それを感じればこそ受入れる地域の人々は心から「ようこそ」と迎えようとする※注4)。そうした“ウェルカムとリスペクトのある関係”こそが、観光の理想的な姿なのではないだろうか。
人々が訪れる地域は、「観光地」(tourist destination)と呼ばれてはいても、そこは人々が暮らす(“We Live Here”)生活の場である。京都も鎌倉も、白川郷も、もともと人々が暮らす地域に、訪れるべき意味を見出した人々が観光をしに来ているだけのことである。いかに経済的利益をもたらすとしても、そこは観光客が楽しむために用意された場所ではない。
観光地域づくりは、「住んでよし、訪れてよし」の地域をめざすことであり、もとより「観光客ファースト」の地域づくりをすることではない。「住んでよし」を阻害してまで「訪れてよし」の地域をつくろうとすることに何の意味があるのか。
観光のために地域があるのではない。観光は地域づくりの手段に過ぎない。そう考えるならば、観光振興の論理が生活の論理に勝ることは許されないはずである※注5)。「地域社会の」持続可能性を考慮しながら、環境保全の枠組みの中で適正規模の観光をめざすことが、今求められている。
コロナ禍から立ち直り、前に進もうとしている今、我々はどのような観光をめざそうとしているのか、どんな理想を掲げ、その実現に向けてどのような取り組みをするべきなのか。我々はもしかすると未来の観光の姿を決める大事な分岐点に立っているのかもしれない。
【注釈と補足】
1)観光客は、「非日常的な条件において、客の立場で、出会う人々との一時的関係をもつ」という状況におかれる。そこから生ずる解放感が羞恥心を薄れさせ、自己抑制が効きにくくなっていることが迷惑行為の根底にあるように思われる(長谷政弘編著[1999]『観光ビジネス論』同友館)。
観光客心理としての解放感は、観光客が訪れる地域を下に見る「下り型」の場合に出やすく、“恥”の意識が薄くなるといわれている(前田勇編著[2019]『新現代観光総論(第3版)』学文社)。考えたくはないが、自己中心的で享楽的な観光行動が引き起こす一連の迷惑行為が、今や「安い国」になった日本を見下すことで生ずるふるまいであったとしたら―そうした思いが杞憂であることを切に願う。
2)京都観光モラルでは、「観光事業者・従業者向け」「観光客向け」「市民向け」それぞれの行動基準が定められている。ツーリストシップは、「住む人・訪れる人・働く人、観光地に集うすべての人が意識したい心構え」とされ、具体的には「人・モノ・自然・文化・歴史・・・その地に存在するすべてを大切にすること」「お互いに思いやりをもって接すること」とされている。両者とも、観光客だけにマナー順守を求めるものではなく、事業者や従業者、住民も含めたより幅広い人々への呼びかけとなっている。
3)写真撮影目的のみの観光客は、いわば「フリーライダー」である。写真撮影目的の観光客は祇園で従前から事業を営む事業者にとっての「顧客」とはならない。お座敷に向かう通勤途中の芸舞妓にとって写真撮影を強要されることは、いわば業務妨害である。
農産物の生産を生業とする農家は、「もう一つの生産物(co-product)」として美しい農村景観を生み出し、地域の観光魅力の創造に大きな貢献をしている。しかしながら写真撮影目的の観光客が増えたところで、生産した農産物を購入しなければ農家の所得にはつながらない。地域の魅力づくりに貢献しているにもかかわらず、その対価が得られないどころか、本業に支障をきたすような妨害を受け、迷惑しか被らないのであるから、観光に対して反発や嫌悪感が生じても無理からぬことであろう。
「文句を言う前にまず感謝」「地域の利益に貢献する住民のもてなしマインドが大切」―そうした考え方は、観光の受益者である事業者のものでしかない。結局、受益者は向きあう方向が違うのだろう。観光から迷惑を被る人々に対してさえ理解と寛容さを求めるのだから・・・。
4)観光は(訪れる側にとっても、迎える側にとっても)異(い)なるものを受入れることである。それは、たとえ不十分であったとしても、郷に入っては郷に従おうとする慎み深い態度があればこその寛容さであろう。
5)京都市の門川市長は、京都が観光都市であることを否定しながら次のように述べている。
「いま観光で高い評価を受けている寺院、神社、自然、景観、食文化、文化芸術には、京都に伝わる暮らしの美学、生き方の哲学が凝集されている。それを一番大事にしなければ、観光も持続可能なものになりません」
「市民生活が根本であり、市民生活を大事にしなければ観光も持続可能なまちづくりもありえないと考えております。したがって、市民生活と観光との調和というのをより一層重視していかないといけない」(箱谷真司[2022]『観光立国・日本-ポストコロナ時代の戦略』光文社新書)。
また、中井治郎氏は「自分たちの暮らしを守るためにWe Live Here と言えるかどうか。つまり、観光と地域社会の持続可能な共存を考えるのであれば、『この場所はまずわれわれのための場所である』と胸を張って言うことができるかどうかが何より重要」と述べている(週刊トラベルジャーナル2024/7/15)。
<執筆者略歴>
東 徹(あずま・とおる)
立教大学観光学部教授。
1962年岩手県生まれ。専門分野は、商学・マーケティング。観光ビジネス、観光と地域振興、地域ブランド、商店街問題等を研究。日本大学大学院商学研究科博士後期課程満期退学後、北海学園北見大学商学部教授、日本大学商学部教授を経て、2010年から現職。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版(TBSメディア総研が発行)で、テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。2024年6月、原則土曜日公開・配信のウィークリーマガジンにリニューアル。